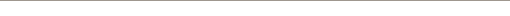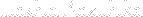先日お伺いしたアサヒカメラ編集部で、「記憶の島―岡本太郎と宮本常一が撮った日本」展のカタログを拝見した。この企画展に足を運ぶことが出来なかったことが大変悔やまれるとても興味深い内容だった。日本を歩き、写真を撮り、記録したお二人の写真をあらためて比較してみるとやはり相当に面白い。当たり前だが視線が違う。特に感じたのは、その目線の「高低」というか、どこに立って撮影しているかが一目瞭然だったこと。
「芸術家」と「世間師」という言葉に全てを帰するつもりは毛頭ないが、やはりそれがにじみ出ている。「ああ、やっぱりそうなんだ」と思いながら食い入るようにそのカタログを見た。
もちろん、そのどちらがどうだとかとかいう話なんかではない。こうした様々な目線が、眼差しが、日本を丁寧に見つめ、そしてその光景をしっかりと残されてきたことに素直に感激したし、それに今こうしてそれらの写真に、目線に出会えることに本当に心から有り難く思ったのだった。写真はやっぱり面白い。
さて。夜自宅に戻り、宮本常一さんの名著「忘れられた日本人」を久しぶりに読み返した。
この中に「村の寄り合い」についての記述がある。
まだ僕が兵庫に住んでいた頃、村の寄合所(壊れそうな古びた小さな講堂)に、ことあるごとに子どもたちから大人たちまで集まってなんだかんだと行事を行っていた。「寄り合い」は大人たちが出かけていくもので、何をしているんだろうと子供ながらに興味を持ったことを覚えている。今でも「寄り合い」という言葉を聞いただけで、様々な自分の子どもの頃の村の風景を呼び起こす。ある意味、それは「マジックワード」みたいなものだ。「なぜ寄合所があんな建物だったのか」「なぜあんな行事があったのか」。そういうことは何も知らず、知ろうとも思わなかったけれど、それ自体が確かに日常のリズムをつくる一要素であったように思う。
宮本常一さんの描写のひとつひとつは、まさにそんな自分の子どもの頃にかいま見た光景とけっこう重なった。
しばらく読み進んでいると、この「村の寄り合い」の代表的な事例として、「兵庫県加古川東岸一帯には~」と宮本さんがまさに僕の幼少の頃に育った辺りを挙がられていた箇所に行き着き驚いた。(前に読んでいた時は、きっとこの「村の寄り合い」のところを飛ばし読みしていたに違いない!)
宮本さんの書かれた村の「寄り合い」の描写が自分の幼少の記憶に重なるのは当然のことだったわけだ。さらによく考えてみると、この書籍の初版は1960年であり、その後も少なくとも10年以上はこの「寄り合い」の風習が僕の実家あたりでは続いていたことになる。
今では村の寄合所は壊され別の場所に新しく建てられている。今でもあの「寄合い」の習慣は残っているのだろうかというと、父親たちの様子を聞く限り、場所やその佇まいは変わっても、そのメンタリティはさほど今でも変わっていないように思える。
そして、こうしたことはおそらく日本各地に細々とまだ残っているはずでは、と想像する。殊更に文化保全や地域再生をうたう運動の中ではなく、ごくごく普通に暮らしているうちの親父たちのような人々の心の中に。
そうした営みを丁寧に見て歩くことを、記録し記憶することを、わずかばかりであっても出来たらと、最近は今まで以上に思うようになった。写真を撮ること、記録に残すことの切実な思いが最近さらに高まっている。「作品」かどうか、ということよりも、これまで以上にもっと歩き、もっといろんな人の話を聞き、そして記録を残したいという気持ちが募っていることを感じている。それはきっと自分自身が父になったということが大きく影響していると思う。