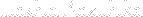さて。
今日から3日間は、まさに年末の大掃除モードである。
合間に暗室に入って、今年最後のプリントもしようと思う。
といいつつ、途中で飽きてしまって、カメラを持って冬の海に出掛けるかもしれないのだが。
垢や手垢はその人自身を表すものだ。
というのは、先日某建築家の友人と話ししていた時に気づいたこと。
小奇麗な外見に仕上げることに懸命で、全く垢など一欠けらもあるわけございません、と顔している人ほど、実はその中はどうやろうとも落すことなど不可能というくらいの垢まみれ、あるいは垢なんて可愛いものというくらいに腐食てしまっている場合があるというのは、先の「姉歯」問題を見れば明らかなことだ。
してきたことの結果として、垢や手垢が自然に残っていくくらいの方が、信じられるし、人間らしい気がする。
「垢を煎じて飲ませよう。」 昔の人は流石いい当てている。
まあそういう話を友人としていたわけだ。
これは決して、大掃除をなんとか言い訳つけて逃れたいとしている「へ理屈」ではないので、この後、早速大掃除に取り掛かろうと思う。
 2005.12.26 (Mon) 兎、皇居、とろろの味。
2005.12.26 (Mon) 兎、皇居、とろろの味。12月23日は天皇誕生日の祝日だが、それよりも、「極東ホテル」の女将さんの誕生日であった。(もうひとつおまけに、僕の親父の誕生日でもあった。)
朝、女将さんに東京駅で買った「チーズうさぎ」と誕生日カードを渡したら(女将さんは「兎」ものの骨董、掛軸、染物などを集めていらっしゃるのだ)、お返しにと立派な自然薯を頂いた。
宿には22日の夜から泊まっていたのだが、深夜洗面所で、英国から来ていた中国系のカップルと仲良くなった。翌23日は朝から暖かく散歩には気持ちいい日となったので、皇居に行きたいのだけど、という彼らを案内しがてら、僕も付いていくことにした。やはり英国から来ているそのカップルの友人1名もそこに合流して、JR南千住駅から電車に乗り、4人で皇居に向かった。下の写真は、英国から来たSolomonが撮ってくれた僕の後姿、二重橋を過ぎた辺り。

今年は、写真展を2回、東京と大阪とで行うことが出来たし、何よりそのテーマ『極東ホテル』と巡り合えた幸運に感謝している。
またこのテーマで撮りだすことになったきっかけは、女将さん、そしてギャラリーの篠原さん、谷口さんなど、人との出会い、である。
あの人たちとの出会いがなければ、きっと僕一人では何も出来ていない。本当に今年は幸運な1年だったと思う。
昨夜、女将さんから頂いた自然薯をとろろにして食した。
すり鉢で丁寧に擂り、出汁と合わせると、ふんわり柔らかく、炊き立ての熱々の新米にかけて食べると、芋の香りが甘く立って、最高に美味しかった。
この味はきっと忘れることが出来ないだろう。
 2005.12.23 (Fri) 冬へ
2005.12.23 (Fri) 冬へ先週の金曜日から、僕はまた「極東ホテル」に通い始めた。
11月上旬から先日の大阪での写真展とその準備が始まったので、2ヶ月近くぶりになる。
その僅かな間に季節は冬へと変わり、それはホテルのちっぽけなロビーに差し込む朝日の光の強さやその色、薄暗い廊下に漂う空気の希薄さにありありと現われていた。
季節の変化は、単に陽光の強弱にだけ現われるのではない。
まるで一筋の束として意思を持って真っ直ぐ差し込んでくる夏の朝日に対して、冬のそれは曖昧で散漫で、夢心地のようにぼんやりしている。
だから、冬の光は柔軟で、そのままロビーにおかれたテーブルから立ち上るコーヒーの湯気や、寝ぼけ眼の旅人がふっと吐きだした息と容易に交じり合ってひとつになり、ロビー全体をぼっと白く照らし出してくれる。
そして、ロビーでまどろむ僕らや、古びたテーブルや、誰かが飲んだ後のコーヒーカップや、あらゆる小さな存在をそっと包んでいく。
閑散期の今、旅行者の数は春や夏と比べて半分から2/3程度と少ない。クリスマスから正月にかけてはもう既に予約で一杯だそうだから、ちょうど今の数週間が最も一年でこのホテルが静かな時期なのだろう。
この日、僕はブルックリンから来ていたパキスタン人の青年と、キャンベラから来ていた男女3人組、そしてコンピュータエンジニアリングを学びにカリフォルニアの大学に通う香港の青年達と出会った。
パキスタン人のハッサンも、香港から来た青年も、みんな日本を経由して、母国に帰る途中だ。
他の人々も含めて、この時期に来ている旅人は日本での滞在日数も短く、みんな1週間以内というところだった。
真っ直ぐに国に帰らずに、束の間だけ寄り道してしながら帰っていく彼らの気持ちは、ほんの少し高揚している。まるで国に帰る嬉しい気持ちが少しでも長く続いてくれたらって、もっとこの気分のままに居たいなって、どこかで思っているからなんだろう。
寒々しい冬だからこそ、その先にある暖かい場所への思いが高まるのだ。
そして、そんな思いが静かに極東ホテルのロビーに満ち出す。
静かに、静かに、極東ホテルの冬が始まった。
 2005.12.21 (Wed) ご報告です
2005.12.21 (Wed) ご報告ですいくつか、ご報告しておきます。
まず、先日の日記で書いた、『言葉』にまつわるクイズ。
何人かの方から、答えがメールで寄せられました。
「げんき?」、「すきよ」、「待つわ」、「大丈夫」(これは、平仮名3文字ではないですが)...。
特に若い女性の方々の答えとして圧倒的に多かったのが「待つわ」です。
実はこれは僕が先輩に答えた言葉とは違うのですが、よく考えると、また多くの女性が何故この言葉だと思ったのか、そのことを考えていくと、確かにこれもあるなあ、という気になってきました。一途で、純粋で、若々しい恋の気持ちがそこにあるように思えました。(なんだかそんな風に書くと、僕はえらい年寄りみたいですね。)
答え(というか、その夫婦の場合の答え)は、
「あなた」でした。
一途な思いの先に、思慮深さがある気がします。ストレートではないだけに、逆に思いも深いのです。
ちなみに、「あなた」という答えをした人は、一人だけでした。
素敵な方だと思いました。
そして。
もうひとつのご報告。
昨日、WEEZERのライブに行ってきました。
楽しかったです。彼らの音楽は「インディーズ」「カレッジチャート」という言葉がぴったりな、ポップなタテのりロックですが、演奏はなかなかタイトで、上手いですね。同じようなジャンルの音楽をやっている日本人バンドと比べて、やはり圧倒的に演奏力が上です。楽曲もライブで聴いてもメロディがしっかりしているので、とても良かったです。
やっぱり基礎力なんだよなあ。ソングライティングと演奏力、またそのことを痛感してしまいました。Rivers君の声もいい。まるで「極東ホテル」の客としてぴったりな風貌だった彼だとは思えないほど、なかなかしっかりアーティストしていました。
なんだかとても嬉しかったです。
ということで、ご報告まで。
 2005.12.18 (Sun) 「世田谷233」、祝・3周年。
2005.12.18 (Sun) 「世田谷233」、祝・3周年。友人の中根大輔が世田谷線沿いにつくったギャラリー『世田谷233』が先週の土曜日で3周年を迎えた。本当におめでとう。
3周年記念のパーティーの席に、夜21時頃に着くと彼を慕う沢山の人たちで狭いギャラリーの中は一杯だった。3年前、彼がこのギャラリーをたった一人で始めた時のことを思い起こすと、僕にとっても何か胸に込上げるものがあった。
彼から学んだことは本当に沢山ある。
僕自身、彼に大変助けられてきた。幾つかの写真展も彼のサポートが無ければ実現していなかった。それに、このウェブだって彼が居なければここまで続けて居なかっただろう。
一人でもちゃんと続けていくこと。
そして、友愛の精神が仲間を連れてくるということ。
彼はそのことを身をもって示してきた。
気の利いた言葉以上に、彼が実現させてきた「現実」そのものの方が雄弁で、智慧に満ち、そして何よりリアルだ。
どんな沢山の書籍よりも、僕は彼のその姿に学ぶことが多いと思っている。
手土産を渡して彼の写真をライカで撮り、直ぐに僕は賑やかなパーティー会場を出た。
また今度ゆっくり二人で話そうと思う。
本当に心からおめでとう。
これからもよろしく。
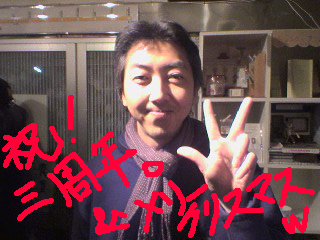
(photo by mobilephone)
 2005.12.16 (Fri) 『言葉』について
2005.12.16 (Fri) 『言葉』について深夜近くまで続いた長いミーティングは、適度な疲労と同時に、ちょっとした高揚感と、同じミーティングに参加していた仕事仲間の先輩に対するいつも以上の親近感を僕の中に連れてきた。
僕らの話題は、当然さっきまで続いた仕事の話から、少しずつ緩やかに逸れていき、「言葉」というテーマの辺りを暫く漂った。
仕事の話から逸れたというのは正確ではない。
表面的には営利のためのその「仕事」が、実はその裏で、あるいはその本質的な部分で、「言葉」あるいは「言葉の力」というテーマを有していたために、関係者がバラけたミーティング後、僕と先輩は今回の「仕事」の本質的なテーマと何故僕らがこの仕事に取り掛かろうとしているのかということについて無意識に確認し合おうとしたわけだ。つまりもうひとつの「ミーティング」を始めたようなものだった。
さて。
「言葉」について、僕は先輩に最近何かの雑誌で読んだ詩人・谷川俊太郎さんの話を話材として挙げた。その雑誌の中で、谷川さんは『「言葉」をあまり頼りにはしていないし、あまり多くの期待をもしていない。だからこそ、なんとかして「言葉」を駆使して伝えようと格闘してきたのだ」という旨のことをお話になっていた。谷川さんは詩人であり、「言葉」で自己表現、あるいは人生をつくられてきた「言葉」の専門家、「言葉」の職人さんだ。その彼が、今もこうしたスタンスで「言葉」に向き合われていることを知り、僕は少なからずの刺激を受けた。
谷川さんはそのあと、こんなこともお話になっていた。
『経済、政治に比べると、ささやかかも知れないが、それでも「言葉」には力がある。個人に届く力があるはずだ』と、これも正確な引用ではないのだが、彼が意図されていたこととは大きく外れてはいないはずだ。
こうした僕からの話材提供を先輩は静かに聞いていた。
彼の中に、この話が速やかに染み通っていく様子は、僕にもよく理解できた。
すると、先輩は「鷲尾、じゃあこんな話は知っているか?」と、お返しとして、こんなとっておきの話を語りだした。
『言葉』についてのひとつのエピソードなんだけど、これは実話だよ。
今から50年以上も前の話だそうだ。正確には俺も良く知らないので、もしかしたらもっと昔の話だったかもしれない。いずれにしても、インターネットもケイタイもない時代の話。一般の家庭電話が一家に一台あったかどうかも定かではないくらいのちょっとした昔の話。
一組の夫婦が居た。彼らは結婚したばかりの新婚さんだったから、お互いにいつもずっと一緒に居たいと思っていた。でも、そんな時期だったにも関わらず、夫の方が仕事のために、遠く南極まで行かなければならなくなった。
そして夫婦は離れ離れに暮らさなければならなくなった。簡単に会える距離じゃない。離れて暮らしている期間だって決して短いものじゃない。
残された妻は夫に会いたくて会いたくて仕方なかった。勿論夫もそうだっただろう。
しかし妻は、仕事のために遠くの過酷な環境の中に出掛けていった夫のことを思うと、頻繁に連絡を取ろうとしたり、「会いたい」と一方的に伝えたりすることは身勝手ではないだろうか、むしろ一人で極寒の地で働く夫のことを思うと、そうしたことは我慢するべきなのだ、と考えた。
そして暫くの間、妻はずっと会いたい気持ちを抑えて耐えて暮らした。
しかし、その我慢にもやはり限界に来た。それは夫が旅立ってから半年後のことだった。
そして妻は一通の電報を遠く極寒の地にいる夫へ送った。
(もし電話が使える状況であったとしても、きっと妻は夫のことを思い電話は使わなかっただろう。先輩はその点には触れなかったが、先輩の僕も同じ考えだったと思う。)
そして、夫はその電報を受け取った。
その電報には、たった3文字の言葉が書き記されていただけだった。
僅か3文字。しかし、その3文字を読んだ夫は、今妻が何を感じていて、何を自分に伝えようとしているのかが全て分かった。妻がどれだけ夫も慕っているのか、また手紙を頻繁に出さないで我慢していた彼女の心遣いも夫には全て理解できた。たった3文字の言葉はとても饒舌で豊かな言葉だった。
そこまで話して、先輩は僕に「鷲尾、その3文字はなんだか分かるか?」と尋ねた。
結論を言うと、僕はその3文字の言葉を即答し、当てた。
その答えを知ると、まるでパズルに最後の1ピースがそっと置かれたかのように、物語の全体が、夫婦の風景がすっと浮かび上がってきた。
そして、僕らはともにその風景を思い浮かべながら、また暫く『言葉』ついての会話を続けた。夜が更けていった。
※この3文字の言葉については、ここに記すよりも、いろいろと想像してみるのがいいでしょう。もしかして答えはひとつではないのかもしれないし。
 2005.12.12 (Mon) カリフォルニアから来た青年(続き)
2005.12.12 (Mon) カリフォルニアから来た青年(続き)前回の日記で、某アーティストに偶然出会い、彼からライブへの招待を受けた、とのことを書いた。
確かに彼らのCDは数枚持っていて、いい曲を書くバンドだなあと気に入っていた連中だったのだが、ヒットチャートを追う聞き方をしていないために、彼らがどの程度ポピュラリティーのあるバンドか、またバンドの成長(あるいは衰退)過程のどの辺にあるのか、ということには全く知らなかったので(ヴォーカリストがハーバード大学進学のためにバンド活動を一次休止したこと、そして久々に戻ってきたということは、CDショップの店頭で見て以前から知っていた)、ちょっとネットで調べると、このWeezerというバンド、チケットは東京3日間ほぼソールドアウト、しかも最新楽曲は次回のグラミー賞の「Best Rock Song」にノミネートされているではないか。
つまり今現在も、名実ともに人気バンドのひとつであり続けている、ということだ。
(勿論、グラミーにノミネートされているということ自体は正確には、だから人気バンド、という理由ではないが、それでもノミネートにはポピュラリティーや市場での評判がある程度は影響している考えて良いだろう。特にロックやポップスといったカテゴリーの場合においては。)
そして、改めて彼らのCDジャケット(オフィシャルに提供されるイメージ)写真を見返してみる。彼は常に黒縁の眼鏡をかけ、回りのバンドメンバーと比べると背が低く小柄であるにも関わらず、スマートな切れ者という風貌でまっすぐこちらを見ている。
それは昔見た『ヤング・ガンズ』という映画に出てきた、エミリオ・エステベス扮するビリー・ザ・キッドを思い起こさせた。あるいは、日本でいえば、牛若丸のパブリックイメージ。
危険が迫っても、体力的な弱みを頭の回転の良さとしなやかな身のこなしで、誰よりも見事に切り抜ける存在を否応なくイメージさせる。
そして、最新アルバムのタイトルは『make believe』。
歌詞の内容が、例え「どうしようもなく駄目な僕ら」や「君だけを想い続けるセンチメンタルすぎる僕ら」の日常を歌っていようと、それも視覚的にこうした牛若丸的なパブリックイメージを僕らは見ながら(知りながら)聞くことで、そのようなテーマをむしろ確信的に唄っている彼の姿を僕らは想像し、一緒にヘタれず、むしろささやかな日常を奮い立たせる勇気を与えてくれるのだ。
しかし彼は、東京の街で、一人で電車に乗り込み、不安げな表情でくしゃくしゃのファックスを片手に航空会社のエアチケットカウンターを探していたのだ。
では、果たして本当の彼の姿はどちらであるのか?
そんなことはあまり勘ぐったりする必要はないし、既に答えは明白だ。
僕が会った彼は、全くの個人、インディヴィジュアルな存在として、見知らぬ国を旅する、一人の青年の姿であった。それが彼の生身の姿である。
メディアの先にある姿をあれこれ勝手に想像してもショウガナイ。
彼は本当にビリー・ザ・キッドかもしれないし、全くそうではないかもしれない。
しかし、少なくとも「たった一人で異国の町を電車に乗ってエアチケットを探す人」であることは確かだ。
きっと、彼はそのようにして、自分で詩や曲を書き、自分の声で歌っているのだと思う。
インディーズ、あるいはオルタナティブというジャンルと呼ばれながらも、すぐにアーティスト面したり、セレブリティ面したり、ファッションアイコン化し、自分自身の歌を形骸化する連中が少なくない中、僕は彼の音楽は信じられると思う。
ライブへの招待も勿論嬉しいが、ライブでも見られないそんな人の姿に出会えたことが、僕にとっては一番嬉しい出来事であった。
 2005.12.09 (Fri) カリフォルニアから来た青年
2005.12.09 (Fri) カリフォルニアから来た青年昨日、オースターの『ムーン・パレス』を読んだ、と書いたのだが、
今日山手線で、まさに僕の中にある『ムーン・パレス』の主人公であるコロンビア大学生M.S.フォッグ(しかも、彼が働かないことを決めて極貧生活を意固地に始めて2ヵ月後くらいの感じ)の印象にそっくりの外国人青年が、手にFAXの地図と、山手線のドア上の路線案内図とをにらめっこしながら座っている姿を見かけた。
彼は本当にもう困りきった表情で、完全に落ち付きを失っていて、単に下車すべき駅名を探しているだけでなく、一刻も早くその場所に辿り着かないと、まるで取り返しが付かないことが起きてしまいそうだ、という感じだった。
乗り過ごさないように駅名を睨んでいるだけなら、それもひとつの旅の楽しみだろうということで、声をかけることはしなかったのだが、彼のその姿を見てやはり僕はその外国人青年に声をかけざるを得なかった。
案の定、彼はエアラインのチケットをカウンターが閉まる前に取りに行かなくてはならないという状況に追い込まれていた。
地図を見ると、日比谷公園の前のビルが印を付けられていた。
時間はあまりない。あと3駅目で降りたら有楽町だと伝えるだけでは、時間通りにそこに彼は辿り着かない可能性が大きい。それで、僕はその目的の航空会社が入っているビルまで彼を連れて行くことにした。
カリフォルニアに住んでいるという彼と僅かの道中しばらく話をした。
カリフォルニア。
偶然にも今朝の僕の頭の中にはカリフォルニアの友人のことが数年ぶりに浮かんでいたのだった。その友人の思い出から始まって、横須賀線の電車の中では、しばらく僕の中で「カリフォルニア」のイメージ連鎖が続いていた。
きっかけは友人の中根大輔が毎週金曜日に発行している「Friday Video Magazine」でリサ・クルーガーの作品『のら猫の日記』を紹介していたことから始まる。
今朝そのメールマガジンを読んで、僕は一度だけ会ったリサのことと、そして彼女の映画の編集を手掛けていたCurtiss Claytonのことを僕は思い出していたのだった。
『のら猫の日記』→リサ・クルーガー→カーティス→LA→そして、そこから始まる様々なカリフォルニアのイメージへの連鎖。LAを通り越して、SanFrancisco、Berkley, ヒップスターの残り香漂うSantaCruzの町にまで、僕の頭の中は飛んでしまっていた。
Curtissと出会ったのは、99年、夏のLAでのことだった。
Curtissは、ガス・ヴァン・サントの『Drugstore Cowboy』や『My Own Private Idaho』を手掛けている天才エディターで、その腕にほれ込んだVincent Galloが、僕らで作る短編映画の編集マンに彼を起用したのだった。
実際、Curtissは人間的にも最高にいい人だった。これまで会ったアメリカ人の中で彼ほど慈悲の心に満ちた存在は居ない。そして天才的な編集のプロフェッショナルと来ている。彼と一緒に居るだけで、何故だかその瞬間、その場所がまさに僕のための「正しい場所」として予め用意されたような心地良い気分になった。Curtissは控えめにそっとそんな場所を提供することが出来る人なのだ。
その後、僕はNYCでリサ・クルーガーを紹介してもらった。
あの時依頼、数回メールでやり取りしただけで僕はCurtissには会っていない。
彼自身が監督した映画『Rick』がサンダンス映画祭で公開されて、僕はその作品が日本に来ることを待ち望んでいたが、結局それは実現しなかった。それと同時に僕と彼が日本で、あるいは他の場所で再開するというタイミングも延び延びになってしまっている。
彼がいつも「My Friend」と書いてよこしてくれたメールはちゃんと大切に残している。
「カリフォルニアには行ったことある?」とその外国人青年が僕に尋ねた。
僕は、「友人も居るんだ。」と応えた。
PS
冬の東京で、カリフォルニアのイメージが連鎖するという奇妙な偶然に、実はもうひとつ思いがけない偶然が重なった。
その外国人青年と一緒にJR有楽町駅から日比谷公園方面に歩いて行く時、彼は自分がミュージシャンで、そのために日本に来ていると僕に語った。そこでふと僕は彼の顔を見て、彼が誰なのかに気づいた。彼はWeezerのヴォーカル、リヴァース・クオモ、その人だったのだ。勿論、僕も彼が創ったアルバムのうち数枚を所有していて、ファンの一人でもあった。いつもリヴァースはアルバムジャケットで黒縁の眼鏡をかけているということもあって、一見僕は彼だとは気づかなかった。しかし『ムーンパレス』の主人公MSと重ねていた僕の勘はあながち的外れでもなかったようだ。
僕は彼がリヴァースとわかって「Welcome Back!」といった。
そう再びWeezerは今年ミュージックシーンに戻ってきたところだったのだ。
なんとかエアチケットを手に入れてほっとした彼に、「日本はどう?」と聞くと、彼は「日本は本当に好きなんだ。来年、日本人の女の子と結婚するんだ。」と話してくれた。
そう話す彼の表情はさっきの電車の中とはうって変わって、とてもリラックスした幸せそうな表情だった。
来週、東京でも3日間のライブがあるようで、僕は彼にそのライブに招待された。
思いがけない偶然によって、僕は今年最後にとても嬉しいクリスマスプレゼントを受け取った。
BGMは勿論、Weezerの『The Cristmas Song』(アルバム『Weezer』より)!!

(新作『make believe』、いいタイトルだ。)
 2005.12.09 (Fri) 『ムーンパレス』
2005.12.09 (Fri) 『ムーンパレス』「太陽は過去であり、地球は現在であり、月は未来である」。
これは、つい先ほど読み終わったポール・オースターの『ムーンパレス』に出てきたセンテンス、NYC・コロンビア大学近くにかって実在していたムーンパレスという名前の中華料理屋で、小説の主人公が食したフォーチュンクッキーに入っていた占いの言葉だ。
ポール・オースターという作家の作品を最初に読んだのはいつだっただろうか、タイトルは覚えている、『孤独の発明』。相当に以前のことだ。以来、実は読んでいなかった。(オースターが原作の映画『スモーク』、『ブルー・イン・ザ・フェイス』は見たけれど。どちらも大好きな作品だ。あと、書籍では近著『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』は読んだが、これは彼が集めた実話集なので、外して考える。)
オースター作品を再び手にしたきっかけは、少し前に大阪に出掛けた時、まさに月が綺麗に輝いていた深夜、道頓堀TSUTAYA1Fの書店でその魅力的なタイトル(=「月の宮殿」)を偶然目にし「今まさにこの本を読むのがぴったりだ」と感じたことと、最近お会いした雑誌『COYOTE』編集長の新井さんのウェブを覘くと、その中で推薦作品として挙げられていたということが、重なったからだ。
こうした「偶然」が重なり出会う本は、やはり単なる「偶然」ではなく、まさに自分の中にまだおぼろげで曖昧ながらもカタチをつくろうとしていた「答え」の輪郭をはっきりさせてくれるきっかけとして、目の前に必然的に現われたのだと、僕は読み進むうちに確信していった。
(「偶然は偶然ではない」ということは、何よりこの小説の大きなテーマでもある。)
実際、この物語の内容自体に、僕はとても惹かれてしまった。
なにより、この話は「旅」についての魅力的な物語なのだ。
そして、主人公はどうしようもないほど哀れな少年であり、苗字が「鳥」という動物に由来するという点も含めて、共感を持たずには居られなかった。
物語の概略など、ここでは書かないが、もしもこのダイアリーがひとつの「偶然」だと感じる人がいたら、一度手にとって見ていただければと思います。
 2005.12.06 (Tue) 大阪の写真展終了しました。
2005.12.06 (Tue) 大阪の写真展終了しました。写真展の最終日に間に合うようにと、先週末は大阪に出掛けた。
大阪に立ち寄る前に、金曜日の夜遅くにまずは京都入りした。
(以下、ユルい感じの旅日記。)
土曜日は朝8時から大原へ向かった。
三千院、宝泉院とまわり、寂光院へ。
なんとか紅葉が落ちる前に間に合った。
寂光院は、壇の浦の合戦で源氏に追い詰められ我が子・安徳天皇を抱いたまま入水した建礼門院が、一人命を助けられた後に京都に戻り余生を過ごした尼寺。
「心」の字を表す小さな池と、やはりこじんまりしてはいるが丁寧に作られた庭を抱えて、山間に静かに佇むこの尼寺の風情に、ほっと安らいだ気持ちになった。
冬に向かう柔らかな日差しを受けながら寂光院に向かった里山の道も心地良かった。
その後は、バスで市内まで戻り、錦市場、寺町二条の一保堂茶舗などを巡り、目当ての食材を仕入れる。一保堂では「雁ヶ音」という名の玉露と、正月に飲もうと大福茶を買った。
夜8時前の電車で京都駅から大阪へ向かった。
digmeout cafeの営業時間に間に合いそうもないので、日曜日、写真展の最終日に出向くことにして、ホテルにチェックインした後は、digmeoutの谷口さんに教えてもらった味穂で遅い夕飯。いつものように、どて焼き、たこ焼き、そば飯。 でもやっぱりこのメニューが堪らなく美味しい。
そしてその後もまたまた谷口さんに教えてもらったBAR JAZZへ。
今日のマスターの選曲は首里フジコさんとケニー・ランキン。
無駄のない動きで酒をつくりながら、1曲ずつレコードを取り出し、きっちりと流れを掴んだ選曲とDJもこなす彼の姿に改めて驚いたが、1ヶ月以上前に1度行ったっきりだというのに、彼が僕がその時頼んだスコッチの銘柄まで覚えていたのには、もっと驚かされた。まさにプロの仕事。
日曜日、写真展の最終日、digmeout cafegへ。
古谷さんとカフェのスタッフに少し早いクリスマスケーキを差し入れ。
店内で自分の写真を最後にじっくり眺めていると、谷口さん夫妻、登場。
しばらく店内で話した後、小1時間ほど南船場を案内してもらう。
やはり町は地元の人に案内してもらうのが一番、これは東京にも他の町にもないだろうという
大阪の粋なお店と人をいろいろと紹介してもらった。
(お休みの日だというのに、ご夫婦でお付き合いいただき、本当に心から感謝してます。)
2日以上も1人で留守番している愛猫ちろのことが気掛かりということで、写真展の撤収をCafeの古谷さんにお任せし、夕方早々に大阪駅へ向かった。
もう本当に、大阪の皆さんのお陰です。
皆さんのお陰で素晴らしい写真展が出来ました。
会場に足を運んでいただいた皆さん、本当に有難うございました。
写真も新たにプリントして良かった。(プリントの腕もちょっと上がった気がする。)
新作を交えたのもまた新鮮で良かった。
ドイツから来た女の子のポートレート。成田空港の待合ロビーの風景。
東京での写真展開催時には、まだ出会って居なかった人たちの写真。
大阪でもDan君は人気だったな。今度メールが届いたら奴にはそのこと伝えようと思う。
(Danは、ドイツの女の子の写真に惹かれたってメールを送ってきてたんだけど。)
実は東京よりも出来がいいんじゃないかって思う。
それは東京よりも新しい写真展だったから当然か。そうでないとな。
また来週から、再び「極東ホテル」に戻ろうと思う。
すっかり寒くなった東京にはどんな旅行者達が訪れているんだろうか。
そう思うと、また写真を撮ることが、見知らぬ「彼ら」に出会うことが楽しみになってきた。
東京を撮り収めてやろう、私の作品をつくってやろう、そういうことではなく、
ただただ、見知らぬ人、見知らぬ場所、見知らぬ風景に、出会えたら、とだけ思う。
その感覚が続いていく限りは、写真はまだまだ続いていく。
大阪駅に向かうタクシーは、すっかり雨に降られ渋滞に巻き込まれた。
黄色い銀杏の落ち葉が濡れてびっしりと舗道に敷き詰められていた。
嬉しい出会いの後には、その分以上の名残惜しさが残る。
そんな僕の気持ちのように、タクシーはのろのろとしか前に進まなかった。

(一保堂の玉露「雁ヶ音」!マジに美味い!)
 2005.12.01 (Thu) 読書
2005.12.01 (Thu) 読書古書で買った藤原新也さんの『幻世』を読んでいると、最初のこの書籍の持ち主がしおり代わりに挟んだレシートがぽろっとこぼれ落ちてきた。
日付は1987年7月4日、有燐堂町田店と青いインクでタイプされていた。この書籍が発売された日付を見ると87年6月30日。前の持ち主は発売とほぼ同時にこの本を買い求めたようだ。
どのような経緯で、あるいは衝動でその人がこの書籍を手にしたのか、勿論僕が知る由もないのだが、今それは僕の手元にある。
この本を繰り返し読んだ末のことなのか、詰まらないと思って早々と手放したのか、あるいは引越などのちょっとしたタイミングのために思い切って整理したものなのか。
僕の膝に落ちてきた1枚の紙片に、ふと本を読む手を休め、僕はしばしそんなたわいの無いことを考えていた。
そんな時間も楽しいものだ。
ところで、10年近く前のこの本の中に書かれていることの効力やリアリティが今どうかというと、全くその力は衰えていない。むしろそれが当時何割かは著者が描くこの国の将来図として「読み」あるいは「イメージ」されながら書かれたはずが、ことごとくといっていいほど「現実」の風景となっていることに気づき、驚く。
それは預言書として書かれたものではない(結果的にはそのような機能をこの書籍は持つようになったわけだが)、丁寧に、深く日常を見つめていくことで自ずと導き出された言葉で綴られている。そのことに、つまり著者の深く深く思索するその力のために、僕は驚く。
僕はこの本を間もなく読み終えるが、手放すのではなく、もう何度か繰り返して読みたくなった。それもある程度の時間をかけて。
熟考された思索や視線から学ぶにはそうしなければならないと思う。
※その書籍の内容をここで簡単に整理して伝えるなどという軽薄なことはしないので、興味がある人は手にとって実際に読んでみてください。