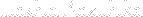7年ぶりに、バンドでスタジオに入った。
カバー2曲(REMとSmashing Pumpkins)、それとオリジナルの新曲を1曲。
家で爪弾く以外は、バンド解散の日 以来まともに音を出していなかったわけで、相当に腕が落ちているだろうし、メンバ ー同士のアンサンブルもばらばらになるはず。でも、意外にそういうこともなく 、7年ぶりにしては、すごくしっくりした感じで音を出すことが出来た。
まあ確かに 個人的には、リズム感も指の動きもぎこちなくなっていたかもしれない。でも4人で 音を合わせたときに「やっぱりこの4人だな」って感じ取ることが出来たことが出来たし、7年間の空白なんて存在していなかった。むしろ皆お互いちょっと大人になっ て「会話」している気すらした。(まあいつも一人で轟音でギターをかき鳴らしてい たのはこの僕なので、正確には皆ではなく僕だけなのかも。)
そして、そこにはしばらく忘れていた音楽を演奏することのとてもフィジカルな喜びがあった。楽器を弾くこと、それ自体がもう快楽なんだなあと改めて思いながらギ ターを弾いていた。
音楽を演奏するのはそれだけで既に最高の幸福なんだな。勿論写真を撮る時にはまた別の心地よい感覚はあるのだけど、全然、異質の快感だ。
7年前まで続けていたロックバンドでは、全部曲も詩も僕が書いていた。だから音楽を聴くときもどこかいつも曲作りを頭に置いて聴いていた。バンドを解散した日以 来、僕は曲づくりを気にしない耳で、これまでに聴かなかった音楽を本当に沢山聴い た。バンド時代とは比べ物にならないくらい。その意味では、バンドを辞めてからの ほうが音楽を素直に愉しんでいたと思う。でも、バンド時代に、初めて自分で描くものを自分自身の手でカタチにすることを学んだことは本当に意味があった気がしている。その後カメラを撮ることにおいても、本を読む時も、文章を書く時も、映画を見たり、作ったりする時も、仕事のことを考えたり、旅したりする時も、そんな全ての 自分自身の営みにおいて、バンド時代に得た「創る」という経験が生きている。それがなかったらきっと今のような写真も撮れなかったと思う。
バンドを辞めて何をすればいいのか分からなくなって、しばらく放心状態の日々を 過ごした後に、ふとしたきっかけで僕は写真に出会ったんだけど、ギターをカメラに 持ち替えても何故か違和感を感じなかった。何故だろうってよくよく思い起こすと 、それは音楽を創っていた時、僕は音やリズムを捉えるというよりも、「情景」を音 楽という手段で捉えようとしていたからのように思う。僕はいつも頭の中に浮かんだ 「情景」を伝えるために、絵筆を使うようにギターを抱えて、詩を書き、コードを探 し、時間や空間を組み立て、演奏していた。その手段がたまたま「ギター」から「カ メラ」という手段になったに過ぎず、そのことでアウトプットされるものも勿論変わ るのだけど、実はそんなに変わっていないような気もしている。
そういえば、バンドを辞めて半年くらいして初めて自分でカメラを買って撮りだし たときに初めて真剣に見た写真展(ワシントンDCのスミソニアン美術館で見たロバ ート・フランクの『MOVING OUT』)の印象は、「このおっさんの写真、ロックミュージックみたいやなあ」だった。
多分これからも、音楽や写真や言葉や、空間でも、モノでも、なんでも駆使して伝 えたいものを表現できればいいんじゃないかって思う。 「写真だけに賭けてます 」ってのも凄いことだなとは思うけど、また僕のような発想だからこそ捉えられる情 景があるだろうし。それでいいんじゃないかなと思う。僕には五感+αがあるわけで 、それを駆使することの方が自然だと思うし。 ダニー・ライアンもそういってたな。
「インディアン達から凄くいい話を聞いたよ。でもな、その話は写真には写らないんだ。」
 2002.02.19 (Tue) 風景2
2002.02.19 (Tue) 風景2 相変わらずテオ・アンゲロプロスの映画にはまっている。
週末は再び「ユリシーズの瞳」を見た。ハーベイ・カイテルが最高だ。この映画は、俳優としての自分の限界、モノを見ることに迷いを持ってしまったギリシア人が、失われた「最初の映画=最初の眼差し」を探すことで自分自身の「眼差し」を取り戻そうとする物語。「失われた最初の映画」を求めて、東欧各地を旅しつづけるというもの。
ヴェンダースが20世紀の最高傑作と挙げたほど、確かに素晴らしい映画だった。
僕がこの映画を見て感じたのは、結局「見ようとしないと何も見えない」ということ。つまり、シンプルでいて、とても大切なコンセプトだった。「見よう」とする力をどこまで僕等は持っているのか。映画の中の物語以上に、この監督自身のその「力」に敬服し、同時に自分にもそのことを問い掛けた。
 2002.02.11 (Mon) 風景
2002.02.11 (Mon) 風景 テオ・アンゲロプロスの作品をまとめて観返している。
昨日は『霧の中の風景』を観た。ここではない何処か(それは存在しない父親が居ると信じている統一前のドイツだが)へ行こうとする姉弟。彼らの眼の前に広がる風景は苛酷であり、残酷であり、果てしない。大人達は打ちひしがれ、絶望と苦悩の表情しか見せない。それでも幼い彼らがどこかに向って歩き続けられるのは、「若さ」や、夢とか可能性などといった「理屈」のためではなく、そんな残酷な世界がそれでも「美しい」からではないだろうか。
しかし、そんな風景にもその中に幾重も折り重ねられた歴史や物語があるわけで、本当のその美しさも日本人の僕にはおそらく理解することが出来ないのだろう。その風景の中に何か「在る」のではないかという感覚を嗅ぎ分けることまでしか出来ないのだ。
 2002.02.02 (Sat) 風
2002.02.02 (Sat) 風 赤穂・御崎にある伊和都比売神社は海を望む式内社の神社で、古くから縁結びの神 として有名なところである。伊和都比売神社は急な海岸沿いの崖に上に瀬戸内の海に 対峙するように建っているが、もともとはその崖を降りた先の海に浮かぶ岩礁の上に 奉られていて、それをかの浅野内匠頭長直が現在の場所に移したそうだ。薩摩藩出身 の元帥海軍大将、あの日露戦争における連合艦隊司令長官である東郷平八郎が開戦の 前に参ったことで海軍の守り神としても知られている。
神社の前に車をおき、ドアを開けると海から吹き上げの風が強く吹き荒れてきた 。
その風は開けたクルマのドアから車内にも入り込み、車内のもの全部を外に運び去 ろうとするほどであった。まるで全てのものを海の中へ招き入れようとしているみた いだ。神社の正面に建ち海の方を観ると、その先の崖に小さな石の門があった。その門から先が「世界」なのだといわんばかりに、その門は海の方へ僕らを迎え入れよう と開かれている。そしてその先には崖に沿って急な石の階段が真っ直ぐに海に向かって続いているのだ。風はそこを通って僕たちの方へと吹き込んできているのだった。
海に向かう石門の光景が、まるでこの世とあの世を繋ぐ入り口のように見える 。
風のせいではなく、僕は身震いすら感じた。そのような直感は当たる。写真を撮る ことは全身の感覚を外に向って明け広げているので、ある意味その都度子供のように なっている気がするのだが、カメラを持っていると実際非常に勘が冴え、鋭くなり 、時たま普段は見られない光景に出会ったり、また気付いたりすることが多々ある 。その石門とその先の風景を見た時にやはりそのような感覚に襲われた。近づくか離 れるかなのだが、僕はやはりその石門を越え、その先に降りていきたくなった。果たして石段を降り、波打ち際に着くや否や、背中から海の方へと引張られる感じがして 真っ直ぐに立つことが出来なくなった。風が巻き込もうとしているのではない。その 見えない力に逆らいながらも僕は枯れた稲穂が風に揺れる中に真っ直ぐ地上へと続く 階段や、背中越しに沈んでいく夕陽と海面の煌きに向いシャッターを切った。それら はやはりぞっとする美しい風景だったからだ。僕はそこに長居せず、直ぐに石の階段 にしがみつくようになりながら上っていった。もう少しその場所に居たらどうなって いたのか自分でもわからない。もしかして上がってくることが出来なかったかもしれない。
ただ、こういうことは決して不可思議な話だとは僕自身思っていない。むしろ 自然の姿を直感できる機会がこうして身の回りにあることを嬉しく思っているのだ 。瀬戸内のあの厳しく美しい風景が僕の気持ちを捉えるのもそんな僕には決して及ばない自然の力が潜んでいるからに他ならないのだ。
 2002.02.01 (Fri) 赤穂
2002.02.01 (Fri) 赤穂 千種川が唐船浜へと流れ込む手前で、陽がゆっくりと西へと傾きだした。
遅い午後の太 陽を背にして、巨大な観覧車が真っ黒な鉄の塊のように空に突き刺さっている。 山陽 自動車道・赤穂ICから市内へ向かう県道沿いに聳え立ち濛々と白煙を吐きながら不気味 なほど静かに稼動している化学工場の姿は長閑な町並みにはあまりにも不釣り合いなよ うに見える。そんな風に長閑な風景の中に突然現れるこれら人工の異型がこの赤穂とい う町をして近隣の町々とはどこか違う空気を作り出している気がした。
赤穂には二つの独自な歴史がある。遙昔、弥生時代に始まり、近世以降には「入浜塩田」という独自の製塩業を確立させた、その産業の歴史。そして今も語り継がれ ている「四十七人の義士」という誇りの歴史。しかし今目の前に見えているこの小さ な田舎町は、まるで役目を終えた老兵のように、その歴史を内に抱え込み、ひっそり と静寂の時にある。不気味な人工の異型とひっそりとした田舎の風景との対比構図は 、自然界と人間界の蜜月の果て、もしくはその戦いの跡の光景なのだろうか。
確か幼い時に潮干狩りに両親に連れられてこの場所に訪れた時にも、そんな長閑 な風景の背後に薄っすらと漂う奇妙な感覚を感じたことを覚えている。灰色の干上がった海の向うに、煙を吐きながら静かに動きつづける工場の姿が遠くに見え、その時何故か僕は大声で騒ぎながら無邪気に潮干狩りを楽しんでいる同級生やその親達と交 じり合っていてはいけないのではないか、きっとこの美しい遠浅の海岸線には自分がまだ知らない秘密がひっそりとあるのではないかと、全くの根拠もなく、しかし直感 的に感じた。遥か上空や、遥か海の彼方にその物語を編んでいる誰かが居て、こうし て僕達をじっと見ているような気がした。それはおそらくヒトひとりが手にしている 日常を越えたところで世界がまわっているという怖れであった。 化学工場の静かさ とその中に押し込められた凶暴さ、そして一気に潮が満ち引きさせる天空からの強力 な磁場、それらの中に囲まれて、あまりにも僕らは小さすぎる。 突然家族旅行で連 れてこられた赤穂の海岸で幼い僕が感じたのはそんな突き抜けていく風景と小さな自 分の存在とのどうしようもないほどの距離であったのかもしれない。
赤穂城跡、大石神社に参り、その後赤穂岬の先端へと車を走らせた。リアス式海 岸のために幾つもの小さな岬と入り江に沿って、「七曲り」と呼ばれる小さなカーブ が続いている。車窓から見られる瀬戸内海の海は、太平洋や日本海とは明らかに異な り、光を思う存分に蓄えた豊潤で穏やかな青で満ちている。この青をどこかで見たこ とがあると思い返すと、それは此処と似通った気候帯であるニースやマルセイユなど の海の色に近いことに気付いた。 2000年を迎えた時、僕は南仏の海岸線沿いを旅し ていたのだが、その時に見た地中海は、まさに柑橘類に豊潤な実りをもたらす光そのものであり、まるで双子のように太陽と海とが強い意志の繋がりで結ばれているかの ような印象を与えた。そう、今目の前に在るのは、あの時の海と空のようだ。
吹き上がってくる風の向うに家島諸島の西島と院下島が見える。
風は強く、まるで海とその向うにある島々が呼んでいるようだ。粗く削られた山肌に荘厳なオーラを 放っていて、この世とあの世とが海を挟んで向かい合っているような厳しく美しい印 象を与える。しかし深く澄んだ青を湛えた海の向うに見えるそれらの島は、近くにあ るのに何故か決して手の届かない気がした。こんなにも空は晴れ、海は青いというの に。そしてその島々はすぐ目の前にあるというのに。何故だろう。
きっとこの光景は何百年、いやそれ以上の昔からも変わっていないのだろう。どれだけの人達がそんな海を見つめながら、届かない光景に手を伸ばしたのだろうか。僕はそんな風景を敬いながらシャッターを押した。そんな風景を感じながら、先ほどの 赤穂の町が思い起こされた。きっとこの町は老兵のようだというよりも、この海とそ の向うに見える島の姿に敵わぬ強さを感じたがため、人間の身の程を知っているので はないか、慎ましく暮らしてきたのではないか、そう思えてきた。
厳しい風景ほど刹那に垣間見せるその姿は美しい。僕が子供の頃に感じた奇妙な感覚とは、それは人間 の営みそのものが持つ業のようなもの、そしてそれらを手玉に取る圧倒的に厳しく美 しい風景との狭間に起こる亀裂に触れた感触だったのだろうか。