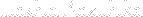一眼レフのカメラをひとつ売り飛ばし、ローライフレックス3.5Fという古いカメラを購入した。僕が生まれるだいぶ前に作られたもので、探し回った挙句、ようやく大阪の中古カメラ屋で見つけることが出来た。決して珍しいものではないはずだが、それでもさすがに何十年前のもの、まともな実用品も少なくなってきているのかもしれない。
基本的に僕はあまりカメラそのものに凝るようなタイプでもないし、あれこれとウンチクを知っている方でもない。それでも何台かのカメラを結果として手に入れているのは、その都度、撮りたいと思う対象と如何にしていい出会い方をするかということを考えての結果でしかない。例えばいつも使っているマキナW67(これも相当に古い、なにせ蛇腹だし)もバイクに乗って海へ行くのに一番最適な中判カメラという理由で選んだに過ぎない。(ちなみにこのマキナW67は「旅道具」と呼んでいる。) 古いローライを手に入れたのは先日のある出来事がきっかけだった。
1月初頭、かっての愛猫達の墓参りに、僕は花束を持って彼らを埋葬した山に登った。
その帰り道、曲がりくねった山道のカーブを曲がると、その先に一匹の犬がぽつんとひとりで山道に立ちすくんでいるのが見えた。赤い首輪を木の枝に引っ掛けられているところを見ると、飼い主はきっと山の中にでも入っていったのだろう、その犬は暗くなる山道で心細そうにこちらを見ていた。僕はその姿を見て、どうしたんや、お父さんは山の中に入ったんか?ちょっと寂しいんだよな、なんて話かけながら、その犬の姿を愛しく思いシャッターを何度かきってみた。するとその犬はこちらが吃驚するほど怯えだし、尻尾を丸め震えだしてしまった。はっと思って自分の姿を見ると、僕がその時手にしていたのは、ペンタックス67という一眼レフをふた周りほど大きくしたごついカメラで、シャッターを切るたびにガチャン、ガチャンと金属の鈍い音がしている。その犬はきっとこれまでそんな恐ろしい音も聞いたことがなかったのだろう。薄暗くなった山の向うから鈍い金属音を鳴らしながら突然ごつい男がごつい「武器」を持って近づいて来る姿は、確かにその犬でなくても、無垢な田舎のひとの子ですら不気味に映るかもしれない。 嚇かしてごめんなあ、といいながらカメラを降ろしても、その犬の震えは止まらない。これはもう大変なことになってしまった。僕もすっかり動揺してしまい、ごめんな、ごめんなと言いながら山道を降りていくしかなった。
それがすっかりトラウマになってしまった。その犬を怯えさせたのは、やはりそれ相当のオーラのようなものを放っていた自分が人として未熟だったのかもしれない。本当はカメラなんて無い方がいいんだろうな。写真なんて撮るのは卑しい行為かもな。それでも撮ってしまうしかない自分。撮るからには誰になんて問われてもきちんと納得させられる答えがないとな。当たり前だが、自分勝手に奪ったところでいいものなんて得られるはずもない。などなど、馬鹿な、でも真剣な自問自答がまた始まった。
そんな理由から、頭を屈めてお辞儀をしながらの撮影スタイルになる、この2眼レフを手に入れたわけだ。周りから見ると馬鹿な話に聞こえるかもしれないし、当然それで解決する話でもないのは承知のこと。しかしこれも本人は至極まじめに考えた努力の結果だったりするのだ。
 2002.01.13 (Sun) 花束
2002.01.13 (Sun) 花束 さかりのついた猫が夜毎窓の外で鳴いている。僕は以前飼い猫に自分の命を救ってもらったことがある。その猫は僕の身代わりになって死んだ。と、僕は今でもそう思っている。
猫の鳴き声を聴く度にいつもその猫のことを思い出す。
その猫の母親猫が突然うちの家に姿を見せたのは、僕が18歳の時だった。
田舎のうちの家には「前栽」が今でもあり(自然の姿を模写した植え込み。実家商売をしている祖母の家と両親と子供達が住む家とのは二棟が繋がった形なのだが、その間にまるで小さな森のように前栽がある)、その小さな森には「玉姫大明神」と彫られた石碑が置かれている。その猫は或る日突然その石碑の上に現れ、以来毎日姿を見せ、ごく当たり前のように家族の一員になってしまった。
「玉姫大明神」は商売をやっているうちの守り神で本尊は京都の伏見稲荷の三の峰に奉られている。玉姫さんが家族の一員として連れてきたその猫に僕は「姫」と名前を付け可愛がった。実に美しい雌猫だった。美しく艶やかな白と黒の模様はまさに日本猫の象徴的な姿で、物静かなその佇まいは和美人の姿に重なって見えた。
姫にも当然さかりがつき、家のすぐ外の畑で彼女が鳴きつづけた暫らくの後、我が家には4匹の子猫が生まれた。3匹の黒猫と1匹の白黒斑の子猫だった。 実は僕はその時既に東京の大学に居たため、子猫が生まれたことも田舎からの母親の電話で知ることになった。子猫みたさに夏休み実家に帰省したり、正月や日本を旅する折に立ち寄ったりした程度だったので、子猫たちとは実際に一緒に暮らした時間は殆どなかった。ただ実家に寄る度、姫とその子供達とずっと一緒に遊びつづけ可愛がっていた。
東京にいても僕はその猫達を戯れている自分のことをいつも考えていたし、その子らがどんな風に過ごしているのはいつも気になって仕方なかった。
そんな或る日、僕は交通事故にあった。
荻窪のピザ屋でデリバリーのバイトをしていた時、豪雨の中を配達の帰りにトラックに正面衝突して意識不明で病院に運ばれたのだ。 その時の記憶は全くない。視界が悪いジャイロの窓越しから雨飛沫ずぶ濡れになった街の断片的な風景しか覚えていない。まるで僕は何かに導かれるようにブレーキを踏むこともハンドルを切ることもなく、まともにトラックに突っ込んでいったそうだ。 後で聞いたのだが、そこは見通しもよいのに何故かよく交通事故が起こる場所らしく、本当に何かが招くかのように僕は事故に遭ったかのようだった。15メートル近く吹っ飛ばされ、頬や顎、手の甲など、突き出たところの肉が全て抉られ、全身打撲で病院に運ばれたのだが、何故かその日の夜には病院から歩いてアパートまで帰ることが出来た。
全身ミイラ男のようであったのだが、骨折もなく脳波の正常で、医者も「入院することはない。自宅で安静にしなさい。」との指示だけ僕に言って帰す他なかったということだったと思う。
我ながら不思議だった。ジャイロはこっぱ微塵に砕けてしまい廃車。トラックの方にも被害があったほどで、実際後で現場に行くと信じがたいほどの距離を僕は吹っ飛ばされていた。たしかに身体は疼いたが痛みはそれほどでもなかった。相当に頑丈な体なのか、もしくは奇跡的な幸運なのか。いずれにしてもその時は我ながら不思議だった。
しかし不思議なことはそれだけではなかった。事故に遭ったことを一応実家の母親に電話したところ、母親は「やっぱりそうやったんか。そうやと思った。」とまるでそのことを予期していたような話っぷりだったのだ。 母親というのは遠く離れていても自分の子供のことは分かるようで、他にもそのような言い方をすることがあったし、僕もまあ親ってそんなもんなのだろうなとは考えていたのだが、それにしても事故に遭ったことを予期していたとは、ちょっとそんな親の直感だけでは済まされない不可解さを感じた。 僕は勿論「なんでやの?」と聞き返した。すると母親は「玉ちゃん(姫の娘の黒猫) 居るやろ、あんたの可愛がってた。あの子が昨日突然道に飛び出しトラックに轢かれて死んだんよ。その時お母さんな、和彦が事故に遭うんやないかと思ったんよ。」とその理由を話してくれた。
玉も突然トラックの前に自分から飛び出したそうだ。彼女はそのまま死んでしまった。即死だった。僕はその話を聞き、可愛がっていた猫に命を救われたんだと思った。目を閉じるとその時の子猫の姿が浮かんできた。僕があんな酷い事故に遭いながらも外傷だけで済んだのは、あの子が身代わりになってくれたのではないか、そう思った。そして今でもそうだったんだと思っている。
誰かと繋がるということはどういうことなのだろう。
直接顔を見て、話をして、手を握って、身体に触れて...。そのように一見ダイレクトに眼で直接、肌で直接接することが本当に誰かと繋がっているということなのだろうか。僕はふとそんなことを考えてみる。 子猫が身代わりになったということ自体、僕の勝手な解釈であるかもしれない。でも実はそういうことはごく自然にありえることなのかもしれない。遠く離れた親が息子のことを近くに居るかのように感じること。それもありえることなのではないだろうか。僕は過剰な空想ではなく、そのことをごく自然な生活の一部として、ありえることと思っている。
そして、あの事故の経験は何より今でも僕の中で支えとなっている。
飼猫が命を救ってくれたということ以上に、誰かとしっかり繋がったんだという事実に、僕は励まされている気がする。人、動物、生き物、自然、何かと自分という存在が繋がったという確かな経験があれば、例え一人であってもそのことを抱えて生きていける気がする。一人だけど一人ではないのだと思える。あの時の事故の経験は僕にそんな支えを与えてくれた。 この正月に故郷へ帰った折、今では全員居なくなってしまった愛猫達を埋葬した近くの山に、花束を持って登っていった。 その事故以来僕は毎年そのようにしている。これからも大丈夫なんだ、という気持ち、そんな気持ちを与えてくれたことに感謝して毎年山に登っている。
僕は花束を山頂から彼らを埋葬した辺りに向かって投げてみた。
その花束は奇麗な弧を描き、すっと真っ直ぐに彼らが眠る辺りに落ちていった。
確かに彼らはその花束を受け取ってくれた。ずっと僕と彼らとの関係は続いていくのだ。
そのことを確かめることが出来て、僕は涙が零れるほど嬉しかった。
 2002.01.02 (Wed) コハクチョウ
2002.01.02 (Wed) コハクチョウ 朝、女池(めいけ)にコハクチョウの姿を探しに行く。
女池と道を挟んだ斜向かいには 鴨池という名の別の池があって、カルガモ、マガモ、コガモ、ヨシガモ、トモエガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、オオ ヒシクイ等、様々な種類の鴨が飛来することでちょっとは関西圏でも名が通っており、冬になるとカップルや孫を連れた老人らが鴨の群れにパンの切れ端を与えている姿が常に見られる。片や女池はといえば、何故か鴨も人影も殆ど見られず、いつもひっそりと静まっていて、やや湾曲したその姿の向こうを木々の後ろに隠しているためか、全貌を見渡せる鴨池とは対照的にどこか神妙な空気感すら感じさせるものがある。 昨日、夕方近くに女池を訪れた時にはコハクチョウの姿は見られず、冬の陽 光を煌かす深緑の水面の上を燐とした空気の層が揺れながら漂っているだけだった。
今朝もやはりコハクチョウの姿は見られなかった。
コハクチョウは150メートルもの遠くからのヒトの気にすら怯え、万が一誰かが悪戯に嚇かすようなことでもあった時には、次の年、彼らは遠くユーラシアの北方からの飛来のルートを確実に変更してしまい、二度とその場所に訪れることはないそうだ。もしかして、ヒト気がないのも近隣に住む純な田舎のヒト達の思いやりがあってかもしれない。
すぐ背後の山の上から朝の光が乾いた空気の中を真っ直ぐに降りて来ている。
いつもよりやや強い風に女池の水面がざわめいている。波立つその頂きに降りかかる光がキラキラと反射して、まるで魚の群れが弾け踊っているかのようだった。その時僕はそんな女池の佇まいに魅了され、その姿を眺めているだけで何か高揚と緊張の交じりあった不思議な気持ちになった。コハクチョウの姿を目撃できなくても只そこに居るということが嬉しかった。
僕はその水面に向かってシャッターを切っていた。
その時だった。右手の水際にある枯れた水草の群生から突然一羽の灰色の鳥が舞い上がった。その灰色の鳥は何度か鋭くきっかき傷のような鳴き声を上げながら、ふらふらと僕の頭上で不器用な弧を描き、朝の光を翳め左手の木々の向うへと飛び去り姿を隠してしまった。逆光の中、それが舞い上がった瞬間、眩しさに眼を細めた僕にはその姿が白鷺か何か見慣れた水鳥に見えたのだが、光を避けるようにファインダーの向こうにその姿を追と、それはまだ純白の羽に衣をかえる前のコハクチョウの子供だった。おそらく親鳥と離れた一瞬だったのだろう、不意の恐怖に怯えながらその「みにくいアヒルの子」は不器用に二、三度空中で身体を捻り、親を呼ぶため声を振り絞り泣きながら愚かで残酷な僕の頭上を飛んでいったのだ。
その必死の飛翔の影を追い続けた。それはもしも僕が例え下手な猟師であったとしても容易に打落とせるほどの、無防備で行き場の定まらない不安定な飛翔であった。僕はその姿をゆっくりとファインダーで見つめながら、そこにかっての自分自身の姿を見た気がした。全てに過敏に反応し怯えなが¥らも無様な飛翔を試みようとしていた、かっての僕自身を見た気がしたのだ。そして、その子を脅かしている今の僕はこの土地を離れ、新しい土地で新しい暮らしを営ん¥できた今の僕そのものの象徴だった。 コハクチョウの子が飛び去った跡には、また揺れながら輝く深緑の水面だけが残った。
あまりにもあの頃と変わらない高い冬の空だった。
僕はもう誰も居ない湖の上で転げまわる邪気の欠片もない光の群れをしばらく眺め続けていた。
 2002.01.01 (Tue) HOME
2002.01.01 (Tue) HOME 干柿、祝昆布、萱、米、かち栗を神棚前の三宝からひとつずつ頂くことで「年をとる」。
山裾を僅かに上ったところにある地元の鍬峪神社に参り、本殿とそれを取り囲むように祀ってある小さな宮に一摘みほどの米粒を捧げながら今日から始まる今年一年の行く末を祈願して手を合わせ廻る。このようにして毎年新年を迎えている。
朝早くまだ霜が残る山裾の畦道を歩きながら、霜が降りかかる雑草の姿そのものを愛しく思うのは、季節感が希薄な場所に永らく住んでいることもあるが、今年は特に両親と友有子との4人でこの畦を歩いていることが大きな気がする。
昼前には父の薦めで篠山の清水寺にも4人で参る。
本殿には参拝客が長蛇の列をつくって並んでいるものの、実はその裏に「清水」の謂れとなった井戸が在ることは意外なほどほとんどの人が気付かずおり、僕達以外はぱらぱらと人が現れるだけだった。僕はその井戸に自分の顔を映しながら故郷の近くにも確かに永い歴史の中で佇み続ける風土、風景があることを感じた。そして、何年かかるか分からないのだが、折をみてはこの場所に戻り、写真におさめていきたいと思った。
それは昨年の11月に高校時代の恩師から「お前の年の頃には、多くのロックミュージシャン達が自分のHOMETOWNのことを歌にしていたんだ。」と云われたこと、そして先日の『INDIAN SUMMER』の先、いやその背景に、幼少の頃見た情景や色や匂いや温度が確かに存ることを個展の最中に自分自身で気付いたことがきっかけになっている。
あの時何を見たのか感じたのか、懐郷の気持ちを写真におさめるためではなく、自分の写真と自分自身が次に進むための「新しい旅」として臨んでみたいと思っている。