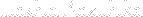Rat Hole Gallery で開催中のAnders Petersen(アンデルス・ペーターセン)写真展『Café Lehmitz』のオープニングに出掛ける。おそらく多くの人と同様、僕のこの人の写真はトム・ウェイツのアルバム『RainDogs』のジャケット写真で知った。『Café Lehmitz』は彼のデビューとなったシリーズで1967年、今から40年前の作品だ。全くその写真の魅力や強度は全く褪せる気配すら感じられない。素晴らしい作品。写真集では見ていたのだけど、プリントで見られて良かった。とても丁寧で、そして思っていたよりも繊細なプリント。プリントにもその写真家の存在が焼き込まれている。プリントを見てますますこの写真家のことが好きになった。
「その写真は人の奥底に眠る感情や欲望をどうしようもなく揺さぶる力を持っている。つまりこれは、ほかの誰でもない、私たち自身の物語でもある。」
写真展のカタログで写真評論家の竹内万里子さんがそんな風に書かれているが、全くその通りだと思う。写真の強さを改めて再認識することが出来た夜だった。
 2007.09.29 (Sat) l'original de sa beauté
2007.09.29 (Sat) l'original de sa beauté深夜、消灯時間間際に、パリ郊外から来たというアルジェリア人とフランス人とのハーフの女の子に出会う。僕と彼女は夜10時過ぎから明け方近くまでノンストップで話を続けた。写真のこと、映画のこと、あるいはBD(バンドデシネ)のこと、絵画のこと。そういったことに関してはとても二十代半ばとは思えないほど彼女は知識もあり饒舌でもあった。しかし、自分自身のことについてはまるで暗闇に手を伸ばすかのようにたどたどしく語るだけだった。むしろこうした話題に関してはもっぱら僕に対しての質問ばかりになる。そして、彼女が僕に問いかけるのは結局のところ、あなたはどのようにして人生をマネージしているのかという点に集約された。
もちろんそんなこと僕だって何か明確な結論などあるわけもなく、せめて自分の些細な経験に基づく「実話」を語るくらいが関の山だ。しかしそれでもそんな曖昧な答え方をする僕との長い会話は彼女にとっては貴重な時間だったのかもしれないと思う。「本や映画のことはよく知っているけど、人間のことはよくわからないの」彼女はそう呟いた。
彼女のその疑問は極めて素直で全うだと思う。他者の存在がわからないという疑問は例えば思春期の頃誰もが感じた素直な疑問であったと思う。しかしそれを問い続けるかどうかは、その後のその人の生き方による。他者の存在(それは人だけでなく、関わり合う世界全体をも指すだろう)のことを理解したつもりでいたり、あるいは勝手な決めつけで解釈することはとても楽だと思う。そしてそんな風に生きていくことに知らず知らずの間に、そして意図せず人は慣れてしまう。「人間のことはよくわからない」と真摯に語る彼女の存在は、明け方近くの眠た気な眼を覚醒させる。「世界をよく見ること/見続けること。」それは生きていくための必死の抵抗であり、唯一の希望ではないかと思う。
“Chacun porte en soi l'original de sa beauté, dont il cherche la copie dans le grand-monde.”(誰もがそれぞれの中に美を宿している。そして人々はその美の世界のコピーを求め続ける。)
そんなBlaise Pascalの言葉を彼女から教わった。芸術というのは、結局人がつくったものであり、そして人の中にある美のコピーでしかない。人の中にあるどのような美を抽出し、それを必死で真似るということでしかない。その通りだと思う。結局長きに渡って人の心を動かすものはそういうものでしかあり得ないし、つまりは人の心を動かすのは「人」の存在そもものでしかないということを、Pascalのこの言葉はとても端的に言い当てている。彼女はその言葉をとても大切にしていると言った。僕はその言葉を手帳に書き留める。そして拙いフランス語でこの言葉を口に出して読んでみる。

 2007.09.26 (Wed) 再会/再開
2007.09.26 (Wed) 再会/再開欧州から戻ってきて、久しぶりに“極東ホテル”へ向かった。
このホテルに通いだしてから早いもので既に三年目に入っているのだけど、今夜は偶然にもかって此処で出会った人々と再会することとなった。一人はフランクフルトから来た二十歳のドイツ人大学生。向こうから声かけられて「以前私の写真を撮ったわね」と言われたけど、顔を見てもどうしても思い出せない。撮影したならネガは穴があくほど繰り返し眺めているはずなのですぐに気づくはず。おかしいなと思って、改めて彼女の佇まいを眺めてやっと分かった。午前も遅い時間だというのにいかにも朝帰りだという眠たげな眼で下着姿のまま布団を巻きつけて廊下に座り込んで煙草をふかしている。実は姿形よりも、そのどこか肝の据わった印象が僕の記憶の中から彼女の存在を立ち上らせた。二年前、まだ18歳だった彼女はもっと体格が良く(つまり、少々太り気味だった)、顔つきもぽっちゃりしていたのだが、この二年の間に(欧米人にしては珍しく)スリムな体型に変わっていて大人っぽく女性らしくなっていた。そういえば以前彼女を撮影したのもこの日の光の刺さない真っ暗な廊下だった。彼女はドイツの大学で日本文化を学ぶようになり、日本語も少し話せるようになっていた。そんな彼女の二年間をふと想像しながら改めて僕は彼女を撮影する。
もう一人は、僕がここで撮影を開始したばかりの頃に出会ったスイス人の男性だった。まだやってんのかとでもいいたげな風にロビーで他の泊り客たちと話している僕の背後にすっと近付いてきた。そしておもむろに彼はこの2年間に彼自身が撮影したというデジカメ写真のポートフォリオを僕に見せる。あれからカメラを買ってずっと撮っているんだ、とニコン製のがっちりとした立派なデジタルカメラを自慢げに見せてくれた。アジアの様々な国、東京、大阪。彼が2年間撮りためたという写真を見ながら、お互いの2年間の間に起きたことを話しあう。期せずして再び偶然で重なった一夜とその背景にある互いに見知らぬ二年という時間。僕はその写真を見ながら、彼の二年間をまた想像してみる。
そして二年前の彼らの面影と、今目の前にいる彼らの存在とをともに感じながら、また初めて出会った時のようにポートレートを撮る。近さと遠さ。既知と未知。どうにも不思議なものだな、と思う。少しずつこうした再会は増えていくのだろう。それはまた“極東ホテル”というプロジェクトがまたもうひとつ次のステップへと移行することをも意味している。そのまま撮り続けるのか、そろそろ次の段階のことを考えるのか。しかしこうしたことは自然な流れに任せるのがいいようにも思う。自然にそのときはやってくる。
最近ふと感じることがある。こうして再会した人に限らず、たとえその夜初めて会った人でも、最近では彼らを異国からの旅人(=ストレンジャー)としては見えなくなってきている。どこかで予め出会っているような感覚。まったくの他者の中に親しさや近さを喚起させるコードが見える。しかしそんなコードを直観的に感じ取りながらも、それでも他者としての遠さをも自覚しながら「出会う」という不思議な感覚をも覚える。
それは僕自身がこの東京の、このホテルの狭い空間の中で一歩も動かずとも、自分自身が彼らと同じ旅人(=ストレンジャー)となっているためであり、そしてその感覚、つまり物理的な空間移動などしなくても、僕自身が移動し続け、漂い続ける存在でしかないことをより明確にこの2年間の間に自覚したためだといえる。他者と出会いながら、同時に僕は僕に出会い続けている。そしてそうした出会い方こそが僕の写真、この“極東ホテル”というプロジェクトの骨格を成り立たせていると思う。ドキュメントであり、セルフポートレートなのだと思う。そしてその「セルフ」という部分には僕だけでなく、この写真を見る様々な人々、それこそ日本人だろうが、台湾人だろうが、セルビア人だろうが、パリジャンだろうが、国籍も性別も年齢も関係なく、この写真を見るすべての人にとっての「セルフポートレート」となればいい、と感じている。僕の写真は僕のものではなく、それを見る人全ての人にとっての写真であればいい。撮影再開。また会おう。
 2007.09.24 (Mon) パリ #03
2007.09.24 (Mon) パリ #03
(Bastille, Paris. 2007.09.)
 2007.09.18 (Tue) パリ #02
2007.09.18 (Tue) パリ #02
(Montmartre,Paris. 2007.09.)
 2007.09.11 (Tue) パリ~ケルン
2007.09.11 (Tue) パリ~ケルンパリ写真美術館でブルース・デヴィッドソンの新作を観る。
超広角レンズを使って、パリ市内の公園の木々や街路樹などを下から見上げる視線で捉えた写真。
木立の間から降り注ぐ光に包み込まれるような感覚を覚える。
NYCの地下鉄、ハーレムに住む人々のポートレートなど鋭く硬派なドキュメント写真を撮り続けてきた彼が今パリでこうした優しい写真を撮っていることに驚きと、そして時の流れを感じてしまう。
単に歳をとったってこと? それとも写真家は結局パリに憧れるものなのか?
いやしかし、そこには彼ならではのシャープな視線や見る者を包み込むような力強さが確かに感じられた。爺さん、頑張ってるなあと、とてもいい刺激を頂く。感謝、感謝。
ケルンでは、GGの菅沼さんや写真評論家の竹内万里子さんに紹介して頂いたGalerie Priska Pasquerのディレクター、フェルディナンドさんにお会いする。『極東ホテル』シリーズから作品20点をセレクトしたポートフォリオを最後に彼に手渡す。
ちょうどお会いした日の夕方17時からGalerie Priska Pasquerにて森山大道さんの写真展のオープニングがあるということで、再び夕方ギャラリーに戻ってオープニングにお邪魔させていただく。『凶区/EROTICA』からの新作プリント。
実はこの日からケルンの3か所で森山大道展が同時開催されるらしく、そのうちの一番大きな規模は300点を超えるプリントが展示されているDie Photographische Sammlung/SK Stiftung Kulturでの『Retrospective from 1965』。
Galerie Priska Pasquerから歩いて10分ほどのところということで、森山さんを含めた関係者の方々にひっついてそのままその日2つめのオープニングに移動。『Retrospective』展も鑑賞する。
以前、川崎市民ギャラリーで森山さんの『光の狩人展』(これもいわゆるRetrospective展)を観た時よりも写真がもっと乾いて見えたのは、その日の午前中にDüsseldorfのK 21 Kunstsammlung im Ständehausでベッヒャー夫妻、T・ルフ、T・ストゥルート、A・グルスキーなどのドイツ写真界の重鎮の作品をまとめ観た影響だと思う。
 2007.09.05 (Wed) ケルン
2007.09.05 (Wed) ケルンドイツ・ケルン。通りを歩いていると窓越しにアウグスト・サンダーのポートレイトが目に入る。
写真につられてその店の中に入ると、そこはオーダーメイドの帽子屋。店内にはハンチングからパナマ帽まで様々な型の帽子と生地、古びたミシンが並んでいる。店内を眺めていると、「彼はこの町が生んだ偉大な写真家ですよ」と店主が微笑みながら現れた。
A・サンダーの写真は店主が複写したものだが、他のどこの美術館で見るよりも、そのポートレートが飾られる場所としてはここがもっとも相応しい。
その力強く誇りに満ちた肖像を眺めること数十秒、ついに僕は奮発して「マイハット」を発注してしまった。
出来上がるまで3週間。ちょうど10月の僕の誕生日の直前に届く予定。
今回の旅での一番の贅沢。