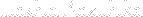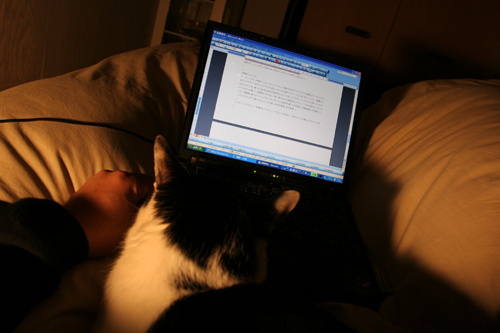週末も写真を撮りに山谷のホテルまで行っていたのだが、この時期は年間で一番旅行者が減る時期なので、ホテルもちょっと落ち着いていた。
偶然にも何人ものオーストラリアからの観光客に会ったのだが、よく考えると南半球のオーストラリアは今が夏、つまり彼らにとっては今がサマーホリデーというわけなので、オーストラリアの旅行者が多いのは別に不思議でもなんでもないわけだ。
Cliveはオーストラリアの大学で国際関係学を学んでいる。
彼はこれまでにここで会った外国人の中で一番日本語が上手い。卒論のテーマが「日本の政治」ということで相当にこの国に関心を持っているようだ。
「将来は外交官になりたいの?」と聞くと、「国際関連情報を分析する仕事に付きたい。」と答えた。今日本では、3点セットといわれる問題(ライブドア、耐震強度偽装、米国産牛肉再禁輸、昨日からは、防衛施設庁談合問題も加わって、4点セットになってしまったのだが)が連日マスコミを騒がせているのだが、彼のそのことについては十分に承知していたし、それ以上に現在の小泉政権に関する分析もかなり的を得たものであった。
また彼の話は当然、日本の外からの視点であり、その点では彼と話をすることはなかなか新鮮で得ることも多かった。得るだけでは何なので、僕は僕が「内」から見て感じていることを彼に話した。Clive君の卒論が出来たらぜひとも読ませてもらいたいと思う。
『Travel without Move』。
Clive君と話しながら、ふとその時そういう言葉が浮かんだのだが、小さなロビーに座って、僕自身は全然動いていないのだけど、なんだか多くの人たちが通り過ぎていく。そしていろんな言葉や彼ら自身の存在に僕は触れることが出来る。(触れたという体験が重要であって、その場合正確には話した内容は、政治的な話題でも、メシの話でもなんでもいい。)
「移動しない旅」。
まさにそんな感じなわけで、これもひとつの「旅」のかたちなのかもしれないなあ、なんて思ったりした。要するに、自分が変わっていけばいいのだし。
ところで、人間わがままなもので、こういう旅もいいもんだよといいつつ、やっぱりどこか実際に身体を使って旅に出てみたいという欲求も出てきてしまう。
実は、今、この春に出掛ける旅の計画中、なのだ。
 2006.01.26 (Thu) 道具
2006.01.26 (Thu) 道具ニコンが実質的にフィルムカメラ事業を辞めると言うニュースを聞いた矢先に、今月19日には、コニカミノルタも3月末でデジタルカメラ事業とフィルムカメラ事業の両方から撤退すると発表した。一気に銀塩カメラからデジタルカメラへのシフトが加速しているようだ。
コニカミノルタは、コニカとミノルタという2社が事業統合して出来た会社だが、そのうちのコニカは、昔、小西六写真工業という社名で、1903年に国産としては初の写真印画紙を発売、確かその頃からフィルムカメラ本体も作っていたと思う。
ちなみに、この小西六という会社は、日本で最初の「CMソング」(昔はコマソン=コマーシャルソングといっていたのだが)をつくった会社でもある。タイトルは『僕はアマチュアカメラマン』。あの日本のポップミュージックのパイオニア・三木鶏郎さんの作品だ。(本当に名曲なので、機会があったらぜひ聞いてみてください。)
コニカ、ニコンに限らず、特にメーカーに対する思い入れはないし、実際に銀塩とデジタル、両方を今使っているし、アナログに固執するつもりもない。単に目的に合った道具を選べば良いと思っているのだが、それでも何らかの出会いがあって、コニカ製、ニコン製のカメラを愛用してきた者としては、やっぱりちょっとは寂しい気持ちになるのが正直なところではある。その辺は正直に言っておこう。
ニコンだとF3というカメラには本当にお世話になってきた。
10年ほど前、ヒロミックスさんや荒木さんも使っているということで一般的にも名前が知られたビッグミニというカメラも以前は使っていたし、その後は実家の母親にプレゼントになった。それから、同じくコニカ製のヘキサーというカメラは、今でも一番よく使う「旅カメラ」として愛用している。
銀塩とデジタル、どっちがどうという議論はまあいろいろとあるのだけど、そういうこと以前に、自分の身体にぴったりと合ったこうした道具が使いづらい環境になるということが、要するに僕にとっては一番寂しいところなのだ。(手元のちょっとしたブレやしっくり来ない感覚が、表現上の大きな差を生むというのは、別にカメラに限った事ではなく、料理でも、陶芸でも、スポーツでも同じだと思うのが、要するにそういう部分が一番重要なところなのだ。)
とまあ、そういうことを嘆いていても始まらない。
人間、というかこの世の中自体が、固定したものなどなく常に変わり続けていく、フローティング・ワールドなのだから、僕らはその変化の環境をむしろ前提として生きていかなければならない。
「黒字経営の足かせだから」という理由で、表現の道具が消えてしまうのが嬉しいわけなどないのだが、それでもフローティング・ワールドはもっとその前提だったりするのだから、やはりそれを受け入れるしかない。願わくば、今後、また新しい出会いの中で、自分の道具が見つかれば良いと思う。
まあそんなことはともかく、写真は撮れるのだから、撮り続けていくだけなんだけど。
と、ここまで日記を書いていて、これもついさっき知ったのだが、ポラロイドがSX70用のフィルムの生産を辞めたそうだ。去年の話なので、僕も相当に情報が遅いようだな。
SX70も実は愛器のひとつだった。(「インディアン・サマー」というシリーズには実は沢山このSX70で撮影した写真がある。発表はしていないのだけど。)
イームズがデザインしたということで、今でもたまに洒落たインテリアショップなどを覘くと、さりげなく空間演出の装置になっていたりするので、見かけたことがある人も、あるいは趣味のカメラとして手にした事がある人も多いかもしれない。
SX70というと、例えばアンディー・ウォーホールの写真とかが有名かもしれないが、僕はDanny LyonがSX70で撮影したコラージュ写真が本当に美しくて最高に好きだった。あの儚げな美しさも、やはりこのカメラの存在なくしては表現できなかった事だと思う。
またしても、僕らは表現のひとつの道具を無くしてしまったのだ。
やはりその道具を使うからこそ、手に出来る表現も確かにあるのだ。
昨年、写真展を行った東京・四谷の写真ギャラリー・ルーニイ247フォトグラフィーでは、このSX70フィルムがこの世からなくなってしまうということを受け、「SX70」展を開催するそうだ。(そういう話を聞いて、本当にここが素晴らしいギャラリーなんだということを改めて痛感した。写真のことを心から愛している人達だからこそ、こういうことが自然に企画されるのだ、と思う。)
もう在庫ストック切れ間近(既に、ビックやヨドバシにはない)というSX70用フィルムを先ほどルーニイに発注した。ポラロイドフィルムは未開封でも保存期間が非常に短いので、手に入れたフィルムもストックし続けることは出来ず、恐らく今年中に使い切らないと駄目だろう。
この2006年末まで1年をかけて、1枚1枚、大切なもの、美しいと感じるものをこのSX70で撮ってみたいと思う。決してノスタルジーではなく、デジタル化、あるいは効率化が加速する中で、消えていき、もう2度と他の手段では代用することが出来ない「美しさ」の感触を味わい、忘れないようにするしかないのだろう。
幸いにも、撮った写真は手元に残ってくれる。そこに写った世界はフローティングすることなく、確かに残る。消えていくものと残るもの。あるいは変わるものと忘れないもの。
2006年はそういうことを考えてみる年なのかもしれないな、と漠然とだが、僕は感じている。
そして、それは決して写真の世界の話だけではない気がする。

 2006.01.24 (Tue) インフルエンザ
2006.01.24 (Tue) インフルエンザどうやらインフルエンザだったようで、1週間熱がひかなかった。
発熱中のベッドの中で取材原稿を1本書き、後は何冊かの本を読みながら過した。
『希望のしくみ』(養老孟司氏とアルボムッレ・スマナサーラ氏対談)はなかなか面白かった。
あと、昨年末から続くオースター著書読破の続き。
『空腹の技法』の中での、オースター・インタヴュー3本もなかなか面白かった。
まだ夜になると、咳が出るので全快とはいかないのだが、それももう時間の問題だろう。
早速今週金曜日には、「極東ホテル」に向かおうと思う。
ところで、最近特に思うのが、「写真的体力」。
昨年からずっと1軒の小さなホテルに通い詰めているわけだが、その限られた場所の中でずっと撮り続けていくのは、なかなか「写真的体力」を要する。
撮りきったなどという感覚はまだないし、もっとその先に出会うものが潜んでいて、未だ出会えていないのだ、とむしろそんな気持ちばかりが続いている。
その気持ちが続く限りは、ひたすらに撮り続けるしかない。
苦しいなどと思って写真を撮ったりしているのではないし、かといって楽しいと思っているわけでもない。ただ歩くように撮っている。あの門を曲がるとっていうほんの少しだけ高揚しながら、微熱のまま歩いている感じ。
「同じ場所に立ったままどれだけ遠くへ広い場所へ移動できるか?」
それが写真的体力ということなのかもしれない。
(何故、猫は原稿を書いていると邪魔したがるのか?)
PS
ある方から、「猫は人間側から見たら 邪魔されてるように感じるかもしれないけれど、猫側から見たら、猫の手ながらも手伝ったり参加しようとしてるのかもしれないです。」とコメントいただきました。そうですね。奴のお陰でとても心地良く過ごせています。でもなかなか役には立ってくれないんだよね~。
 2006.01.13 (Fri) 箱猫
2006.01.13 (Fri) 箱猫何故、猫はそこに箱があると入りたがるのか?
昔、大学生の時に家で飼っていた猫のショータは、開いた新聞を山折にしてつくった「トンネ
ル」が大好きで、お尻をプリプリと2~3度振ってからダッシュしてその中に飛び込んでいった。現在うちで飼っているチロはそこまではしないが、それでも箱があると入りたがる。
でも、よく思い返すと、そういう僕も小さい時には田圃や川原の竹やぶなんかに入っては「基地」をつくり遊んだものだ。悪戯をして親にどやされ、納戸の中に入れられたりするなんて経験をしたことがある人も多いと思うけれど(勿論僕もしょっちゅうのことだったのだが)、押入れに入れられると実は内心ワクワクしながらも、狭い暗闇の中からあれこれ外の世界に聞き耳を立てたりしていた。当時のうちの納戸には小さな窓が上の方についていて、布団とか収納ボックスの上に乗ってその小さな窓から普段の見慣れた風景やその中で動いている顔見知りの小父さんの姿を見ていると、なんだか不思議とその風景が自分だけのものになったような気がしてどきどきしたことも覚えている。今この日記を書きながら思ったのだが、納戸の小窓から世界を見る体験が、もしかすると僕も最初の「写真」的な体験だったのかもしれない。今は小さなファインダーから僕は外の風景をじっと見てワクワクしている。何も変わっていない。
でも全くそんなことはあまり猫の話とは関係ないな。
ところで、何故、猫はそこに箱があると入りたがるのだろうか??
 2006.01.12 (Thu) 写真家の話
2006.01.12 (Thu) 写真家の話【news】の方にも書いたのですが『Quest』というフリーマガジン(といっても結構丁寧に作られています)に僕のインタヴューと作品が載っています。
昨夜自宅に届いてその雑誌を眺めていると、他にも何人かの写真家のインタヴューが載っていたのですが、それがなかなか面白い。
ちょうどフランク・ホーヴァット著『写真の真実』を再読していたところだったのが、改めて読むとやっぱりこちらも相当に面白いのだ。
何が面白いかというと、写真家のインタヴューとは、結局、それら一人ひとりの個人がどのようにして世界を眺めているのかという話であり、彼らの話を聞くことで「写真家の数だけ、あるいは眺める眼の数だけ、世界が存在している」ということを教えてくれるからだ。
如何に世界が依然として未知であり、まだ暴かれていない領域が沢山僕らの周りにあるのか、ということに気づく。決してQuestされ尽きることはない世界。
写真家たちの話は彼ら一人ひとりが見つけた世界のレポート。だから面白い。
僕はその「世界の多さ」にもうワクワクして興奮してしまう。
別にそれは前人未到の大冒険の話や写真である必要など全くない。そして、現実と写真とどっちが本当の世界なのか、なんて話も全く意味がない。
例えそれが一人寝の小さな部屋であろうと、毎日行き通う町であろうと、よくよく自分の眼で見詰めるだけに世界は常に新しい姿を見せてくれる。全て流れつづけ変化し続ける。見詰め返す程に全ては新鮮になる。そんな「よく自分の眼で見る人」のことを写真家というのかもしれない。
見ることは、写真を撮るってことは、幸運を手にするためのとても有効で具体的な方法なんだなあと思う。沢山の写真家の話を読みながら、僕は(自分が写真家であるかどうかも放っておいて)そういうことを思って微笑んでしまうわけだ。
誰もがみんな写真家になれば、世界はもっともっと楽しくなるんじゃないかな。
 2006.01.11 (Wed) Bonnie Pink
2006.01.11 (Wed) Bonnie Pink
(2005.12. Akihabara)
 2006.01.10 (Tue) 『最後の物たちの国で』
2006.01.10 (Tue) 『最後の物たちの国で』昨年末ごろから、ポール・オースターの作品を読み耽っていたのだが、新年を跨いで更に数冊を読み終えた。『最後の物たちの国で』、『鍵のかかった部屋』、『孤独の発明』(再読)。その中では特に『最後の物たちの国で』が強く心に残る作品だった。
「人々が住む場所を失い、食物を求めて街をさまよう国、盗みや殺人がもはや犯罪ですらなくなった国、死以外にそこから逃れるすべのない国。アンナが行方不明の兄を捜して乗りこんだのは、そんな悪夢のような国だった。極限状況における愛と死を描く二十世紀の寓話」(作品紹介より)
『最後の物たちの国で』は全く時代も特定の国も言及されていないし、一読するとSFのようだし、カタストロフ的な主題のハリウッド映画の小説版のように読むことも出来る。しかし、僕には何故かノンフィクション作品を読んでいるように思えてならなかった。
(そう思って他の作品、例えば彼のNY3部作を読んだことを思い返すと、時代や土地等の設定をある程度明示しているそれら作品の方がむしろフィクション的だと感じながら僕は読んでいたように思える。)
この作品を読んでいる間に新年を迎えたのだが、なんだかその読後感が2006年初めの気分として今もずっと僕の中に糸を引いて漂ったままだ。
確かにどうしようもないほど暗くて悲惨な話だが、それでも最後には気持ちがポジティブにゆっくりと静かに高揚していった。それはどんな感覚なのだろうか(ポジティブという言葉だけでは全く足りないとは分かっている)。
そして何故そんな感覚を持ったのだろうか。
ここのところずっとそのことを頭の隅のどこかで考えている。
あまり早急に答えを出すことはせず、オースター作品に限らず、様々な書籍、音楽や映画、あるいは毎日のニュース、新聞、また誰かとの会話を通して、じっくりその感覚を紐解いてみたいと思っている。
なんとなく、直感的に、それが今年1年のテーマのような「勘」がしている。
 2006.01.05 (Thu) 謹賀新年!
2006.01.05 (Thu) 謹賀新年!