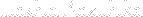昨夜のNews23で、「あまりにも情報や選択肢が多すぎて、自分であまりよく考えられないし、選べない」って発言している高校生の発言が印象に残った。
高校生だけじゃなくて、大人もそういっていた。
今朝、HEATWAVE の新しいアルバム『Land of music』が自宅に届く。
何故自宅に届いたかというと、以下のようなプロジェクトに一口僕も参加していたからだ。
以下、HEATWAVEのウェブサイトから転用。
「レコード会社の資本に頼ることなく、自らの手により制作前から、アルバムを熱望するファンから賛同金を募り、制作資金に当てて作品を作り上げる画期的なプロジェクト。(中略)
ヒートウェイヴはこれまで、メジャー/インディーを問わずレコード会社の資本により音源を制作してきました。しかし、従来のやり方では自身の楽曲を自由に使用できないという制約がありました。例えば初期のアルバムを新たなファンの皆さんにも聞いていただきたいのに提供できない、また発表している全ての楽曲を配信したいのに叶わないなど。
そこで今回、独立した形で音源を制作したいという考えに立ち至り、このプロジェクトを立ち上げました。そして数多くの賛同を得て完成した作品が、このアルバム『land of music』です。こうした新たな取り組みにより、様々な権利を第三者ではなく自分たちが保有し、我々の財産を使い自由に活動の幅を広げていき、音楽を取り巻く環境を変えていきたいと思っています。」 (2006 HWアルバム製作実行委員会)
とりあえず朝っぱらから通しで一回聴いてみた。
軽やかで、そしてタフ。身が引き締まった。
確かにブックレットには僕の名前も記されていた。
このアルバム、とても大切に繰り返し聴くんだろうな。
僕は凄くこういう発想っていいなと思う。
最近はやりの「オンデマンド」って、つまりはこういうことなんだなと実感した。
音楽でもなんでも、自分でいいと思うものを探していくしかないんだよね。
 2006.12.23 (Sat) 大竹伸朗「全景」展
2006.12.23 (Sat) 大竹伸朗「全景」展東京都現代美術館で開催中の大竹伸朗「全景」展に行ってきた。
といっても、もう3回目だ。
毎回行く度にパワーを貰う。こんな展覧会は経験したことがない。
今週末で終るということなので、やっぱりもう1回行こうと思って出掛けたら、会場を出たところで後輩のK君にばったり出会う。今年中に会わなくてはと思っていたところ、うれしい偶然。
でもそれは偶然というよりも必然なような気がして、お互いにあまり驚くこともなかった。
会いたい人には、会いたいなと思うときに会えるものなのだ。
そのまま近くの中華料理屋でビールをひっかけながら2人で夕食。
とても楽しかった。やっぱり必然だなと思った。
ちなみに。
大竹さんはほぼ毎日夕方に現われてダブ平を演奏している。
前回は普通の平日の夕方に大竹さんの生演奏を聞いたのだが、今日は終了直前の金曜の夜ということで観客も多く、いつになく激しく高揚した演奏だった。
最高にかっこよかった。
大竹さんの作品を目の前にすると、迷いなどなくなる。
ただ自分が出来る精一杯のちからで、精一杯のいい作品だけを創っていけばいいのだと思う。最終日にも多分また出掛けると思う。
 2006.12.22 (Fri) Bruce Springsteen『Born To Run /30th Anniversary Edition』
2006.12.22 (Fri) Bruce Springsteen『Born To Run /30th Anniversary Edition』クリスマスプレゼントというわけではないのだが、昨年末にBruce Springsteen『Born To Run /30th Anniversary Edition』を自分のために買った。
この中には、『Born To Run』のデジタル・リマスター版のCD1枚、75年のロンドン・ハマースミスオデオンでのライブ映像DVD、そして『Born To Run』制作ドキュメントDVD1枚が収められている。
Bruce Springsteenという人は、詩人、ソングライター、プレイヤー、どれをとっても突出した才能の持ち主と僕は思う。しかしキャリアが長い分だけ、実際には彼のどのアルバムから聞き出したか、あるいは70年代、80年代、90年代、2000年以降と、最初にいつの時代に出会った等で、相当大きく彼に対する印象が違っているのではないだろうか。
80年代後半や90年代初頭、つまり『Born in the USA』以降に彼の存在を知った人にとっては、商業ロック、大仰な80年代サウンドの代表的アーティストとして、彼の存在が刷り込まれた可能性も非常に大きいかもしれない。その当時は、ヒップホップ、マンチェスター・ムーブメント、グランジ等といったストリート発の新しいオルタナティブ・ミュージックが登場し、ニルヴァーナ、ベックがビルボードのメインストリームを喰いにかかったまさにその時であり、Bruceの音楽は、確かにオルタナティブ・ロックの想定敵のような存在として映った瞬間もある。勿論それはアーティスト本人の思惑とは全く関係ないし、事実的外れもいいところだった。「Don't trust over my generation」あるいは「Everithing is the subject to debt」というのがロックのひとつの基本的なアティチュードだが、こうした安易な対比はむしろ真実から目を遠ざけ、結局は双方にとってもあまり得ることは無い(事実、当時90年代を代表するオルタナティブのイコンとして祭り上げられた才能あるソングライターが自殺している)。
僕が『Born To Run』というアルバムを聞いたのは、そのアルバムが発売されてから何年も後、僕が中学生の時のことだったと思う。確かに僕も最初は当時大ヒットしていた『Born In The USA』で彼を知ったと思うが、そのアルバムよりも、アコースティックギターとハーモニカだけで演奏されている『Nebraska』や、ずっと以前にリリースされたこの『Born To Run』というアルバムの方が圧倒的に好きだった。
特に『Born To Run』を聴いた瞬間、今思えば、始めてロックミュージックの持つダイナミズムや、ロマンチシズムを感じた気がする。そして、シンプルな言葉で深い情景を描き出す彼の「ストーリーテリング」の才能に圧倒された。1曲ごとにまるで良質の短編小説を読み聞かされているかのように思えた。1曲1曲の中には、ちゃんと主人公達が居て、彼らが住む町がありありと見えていた。主人公達は殆どが何処にでもいる打ちひしがれたティーンエイジャー達であり、それは(きっと世界中のオーディエンス達がそう感じたと思うが)僕自身とも重なった。
その後、僕は音楽を自分で創り演奏することになるが、音楽性や嗜好性ということよりも、ロックミュージックが持つダイナミズムとロマンチシズム、ストーリーテリングという表現形態(この物語は誰の物語にもなりえる。そして物語はオーディエンスの中で成長していく、ということ)に強く影響を受けた気がする。僕はいつもひとつの情景を描くように詩を書き、楽器の音色を選び、演奏した。
そして、ちょっとした偶然のためにギターからカメラに持ち替えた今でも、実は表現方法が違うだけで、同じことを僕は続けている気がしている。
デジタル・リマスタードされたアルバム『Born To Run』は当時聴いた音よりも一層タイトに仕上がっている。リッチではなくタイト。音の壁を構成するパーツが一旦解体され、再びひとつずつ丁寧に積み上げられていき、密度と強度を増している。それ故に、ロックミュージックそのものとそのダイナミズムに対する確信性が更に高まっている。そして、それは当時のサウンドプロダクションの緻密さと構成力の凄さを意味している。手を掛けて丹念に作られたモノだけが、風化を余儀なくする時間の流れを耐えていけるのだ。
あやふやで不安定で、流れ続けて、いつの間にか誰かの思惑に絡み獲られてしまう、そこから個人が自力で抜け出せるかどうかの格闘が現代の大きなテーマだとすると(あるいはそれは単に僕自身のテーマでしかないのかもしれないが)、何故だか今この30年前のアルバムに綴られた個人と名も無き主人公達の物語の数々、そしてそれを弾き語ることに確信的なアーティストのアティチュードに、今こうして自分が改めて聞いている必然を強く感じた。
この『Born To Run /30th Anniversary Edition』に収められているロンドン・ハマースミスオデオンでのライブ映像は収穫だった。ニュージャージーのローカルヒーローが初めて海外に渡り演奏したステージ映像。
音の迫力が凄いし、バンドの演奏も素晴らしい。このDVDのサウンド・ミックスは、あのボブ・クリアマウンテンが手掛けている。「おまけ」ではなく、これは一本の優れた音楽ドキュメント作品なのだ。
当時、ローリングストーン誌の音楽評論家ジョン・ランダウはBruceのライブを観て「僕はロックンロールの未来を見た」という有名な評論を書いたが、
このDVDを見るとその言葉が決して過剰ではないことを痛感する。もしもこのライブを目の前で実際に目撃したならば....。
ということで、全くもって最高のクリスマスプレゼントになったのだった。
 2006.12.15 (Fri) 風景写真
2006.12.15 (Fri) 風景写真ここのところは「ポートレート」がテーマのシリーズをずっと発表してきているし、先日の写真展終了後、密かに静かに撮り始めた新しいプロジェクトもやはり「ポートレート」なのだが、勿論被写体を限定しているわけではない。
実際に自宅のネガの棚を見ると、そんな旅の風景を撮影した写真の方が圧倒的に多い。これらの写真は殆ど外では発表したことはない。いつかそういうタイミングが来るかもしれないなとは思いつつも、今のところは、むしろ目の前、むしろごく身近な写真の中に、時間や場所を飛び越えていくような「旅の感覚」を感じとりながら撮影していきたいと思う。
ポートレート撮ってても、旅は出来るしね。むしろ飛距離は長かったりして。

(2006.12.06. Hanamaki, Iwate)
 2006.12.11 (Mon) 写真展終了しました。
2006.12.11 (Mon) 写真展終了しました。emon photogalleryでの写真展が無事終了しました。
会期中足をお運びいただいた皆さん、本当に有難うございました。
心より感謝いたします。
『極東ホテル』というテーマで、2006年度だけで都合4回、昨年から合わせると6回も写真展を実施しました。少しでも多くの人に見ていただきたい、そのような写真家の我が侭をお聞き届け頂いたギャラリー関係者の皆様にも心より感謝申し上げます。
また今年は、『フォトドキュメンタリーNIPPON』というプロジェクトに参加し、写真集の形で作品を発表する機会も頂きました。ガーディアン・ガーデン関係者の皆様にも感謝いたします。
『極東ホテル』というテーマはまだまだ撮影継続中です。
しばらくの間、一人でじっくり更に深く撮り進めて行きたいと思っています。
ちなみに先週も、そして今週も、「極東ホテル」通いは続いています。
先日のNHKでのドキュメンタリー放送(何人か方からメールで「鷲尾さんの写真がテレビになったんですね」と頂きましたが、僕は関わっていません)以降、最近は日本人の宿泊客も増えているようですし、先日も某民放テレビ局の番組収録でどこかで見かけたお笑い芸人さんがマイク片手に騒々しく宿泊客に詰め寄るシーンに遭遇したりと、少しずつこの場所の姿も変化しつつあります。
こういうことも含めてやはり写真と時代というのはセットなのだなと思ったりします。
また何かの形で皆様に発表できる機会が持てるときには、このウェブサイトでアナウンスさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。
では!
 2006.12.10 (Sun) 岩手(2) バタークルミ
2006.12.10 (Sun) 岩手(2) バタークルミ吾妻嶺の佐藤さんにお会いして、翌日東京に帰る前に、僅かな時間だが花巻に立ち寄った。
花巻駅から歩いて20分ほどのところにある北上川の河原沿いを歩く。北上川と猿ヶ石川とが合流するその辺りは、かって宮沢賢治が「イギリス海岸」と名付けた場所として知られている。
「銀河鉄道の夜」にはプリオシン海岸に下り立ったジョバンニとカムパネルラが化石発掘を見学するシーンがあるが、それもこの辺りの河原をイメージしたものだといわれているそうだ。実際、この河原で賢治はバタークルミの化石を発見している。
宮沢家は岩手県の中でも随一の裕福な家庭に生まれた。これは岩手県に住む写真家のOさんから聞いた話だが、当時賢治は自分で作ったトマトをリアカーに引いて売り歩いていたそだ。当時のリアカーは非常に高価で県内にも僅かな台数しかなかったらしい。それを思うと、そんな彼の姿は周囲からは奇異なものとして映ったことだろう。分かりやすく例えると、フェラーリにトマトを積んで売り歩くようなものだ。それはある種滑稽ですらある。
吾妻嶺の佐藤さんと宮沢賢治の話題になった時、彼は岩手県人には賢治を慕う人とそうではない人との二種類の人が居ると聞いたのだが、その理由は、こうした賢治の氏素性と彼の表現活動やそのテーマとの対比によるものだと容易に想像できる。確かにその姿は滑稽さを通り過ぎ、人によっては怒りを感じさせるものですらあったのかもしれない。
賢治は、先のイギリス海岸と名付けた北上川の河原に更にもう一つの名前をつけている。
それは「修羅の渚」。
「なみはあをざめ 支流はそそぎ たしかにここは 修羅のなぎさ」
イギリス海岸には、賢治の「イギリス海岸の歌」からの言葉が刻まれた碑があった。
修羅とは、仏教でいう「六道」の、「人」と「畜生」の間にある生きものであり、知性を持ってはいても、怒りや闘争心を強く持ち、他者に勝ろうとする勝他の念、あるいは妬みやつらみを抱えている存在、つまり他者への愛情を欠いた状態のことを指している。
ちなみに「六道」でいう「人」とは、善悪の分別が出来る理性、慈悲、愛の心を持っている状態を意味する。
賢治が生前に唯一出版することが出来た詩集『春と修羅』をはじめ、この「修羅」は常に賢治の中のテーマであった。それはつまり、自分は「修羅」であり「人」ではない、そして「人」になることに生涯をかけるということだ。それは賢治特有の思想などではなく、彼が一人の仏教徒であったということを意味しているに過ぎない。
しかし、そのことを一人の人として全うしようとしたこと、そしてそれを「表現する」という、つまり自己顕示欲を強烈に持ち続けたこと、その狭間で常に揺れ動きながら生きたのが宮沢賢治という人だったのではないかと思う。
その意味では、賢治は常に「修羅」であり続けたのかもしれない。
そして周囲の他の誰よりも恵まれた環境に生まれ育った彼は、必要以上にそのことを意識していたのだろう。賢治の純粋なまでの想像力、発想力は、幼少期に好奇心の赴くまま書に耽り、海外の文化にも目を向けることが出来た賢治の恵まれた環境がやはりあったためだろう。そして同時に、あるいはそれ故に、彼が抱え続けた「修羅」としての業から生まれたのではないだろうか。
そんな自分と対峙する場所が、このイギリス海岸、プリオシン海岸であり、そして修羅の渚だった。
今、彼の作品は僕の手元に残り、そしていつも僕を刺激し、感化し続ける。
彼は、自分の生い立ち、環境という自分の「持ち場」の中で、あの作品群を残した。
表現力の逞しさ、そしてそのクオリティだけが結果的には時代を超えて残り続ける。
時間は、その人の存在、あるいはその人に纏わりつく余分を払い落とす。そしてそこに残るものだけが表現であり、クリエーションであり、あるいはアートなのではないだろうか。
僕らはただ彼が残したものだけを自分自身で見て判断すればいい。
要するに、つくったトマトが美味いかどうか、なのだ。
自分の舌で味見をしない、あるいは隣の喰っているモノを欲しがるのが、「修羅」なのではないだろうか。
イギリス海岸を下ると、その直ぐ近くに住んでいる地元の小父さんに声を掛けられた。
「何処から来たんだ? ほら、これあげよう。」
小父さんの手の中には黒ずんだ何かの塊が握り締められていた。
それは干からびた一個のバタークルミだった。
 2006.12.08 (Fri) 岩手へ
2006.12.08 (Fri) 岩手へ取材で、岩手県紫波町へ。
造り酒屋、吾妻嶺、13代目蔵元の佐藤さんにお会いする。
佐藤さんは現在35歳。東京の大学を卒業し実家の造り酒屋を継いだ。
彼が生まれた年に日本酒の消費量は史上最高を記録し、昨年2005年はその全盛期の半分になったそうだ。ワインを代表とする様々な輸入酒の普及と同時に、日本酒を提供する酒造メーカーサイドが、日本酒の魅力をきちんと伝えてこなかった事の両方に原因があると佐藤さんはおっしゃっていた。「僕の世代でそのツケはきっちり返す。」
時間が過ぎるのも忘れて夜遅くまで彼の話を聞き、刺激された。