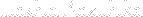【news】にも書きましたが、ハワイでジャック・ジョンソンとコクア・フェスティバルを取材したレポートが掲載された『mammoth』(ニーハイメディア発行)が9月30日に発売されます。
早いもので取材自体はもう半年前の4月。本当にようやくという感じで、ほっとしています。
今回の取材は、本当に幸運としか言いようのない出会いが沢山ありました。
ホームステイ先のマチさんとそのご家族、パタゴニア・ハレイワのスタフの皆さん、コクア・ファウンデーションのスタッフの人々、取材に応えてくれたジャックとそのスタッフの皆さん、ジャックのお母さんやご家族、ALOのメンバー、バッファローレコードの野口さん、ニーハイメディアのルーカスさんと櫻井さん。こうした皆さんとの出会いやサポートがあって今回の取材が実現できました。 この後、直ぐにハワイに掲載誌と手紙を送りたいと思ってます。

 2006.09.28 (Thu) 再開
2006.09.28 (Thu) 再開今週末から、再び『極東ホテル』通いを再開
この夏は執筆作業のために全く撮影できていなかった。では原稿が完成したのかというと、実は全く出来ていない。正確には既に3回も書き直しているのだが、先週末から、「これじゃ駄目だな」と、改めて全体構成を作り変えているという次第。しかし、少し先が見えてきた。構成が上手く行けば、あとはスピードアップは可能だ。その辺のめどがついてきたので、『極東ホテル』を再開しようと思う。
それにもうあの場所に行けないことへの我慢が限界に来ている。
 2006.09.14 (Thu) ベルリン
2006.09.14 (Thu) ベルリン
(Berlin, 2006.09.)
リンツやウィーンはドナウ河畔の町だが、ベルリンには街の中心地の北側をシュプレー川という小さな川が横切っている。川というよりも運河。シュタットミッテあたりから真っ直ぐ北に向って歩き、この灰色のコンクリートに囲まれたその侘しげな川を越えた辺に、ぽっかりと浮かんだような白い砂浜と小さな公園、そして屋外の演劇舞台とが同居した一角があった。
何故だかいつ訪れてもこの町を歩くたびにディプレッシブな感覚に包まれる。川も町並みも、そしてどこか人の表情までも。旅の最終地ということもあり普段よりも足取りが重くなったまま、そんな気分のまま何本かの路地を抜けたところで、この一角に迷いこんだのだった。
白い砂浜、飛び跳ねる少年の姿はあまりにもこの町の表通りとは不似合いだった。こうした場所が他にも町の隅に密やかに存在しているはずだ。この場所を通って町は新鮮な空気を吸い込み、そして運河の上にそっと息を吐き出すのだ。
 2006.09.06 (Wed) 何故、熊を放つのか?
2006.09.06 (Wed) 何故、熊を放つのか?ウィーンに着いた。ここは次に向うベルリンへの経路地。週末もリンツでずっとフェスティバルの取材をしていたために、2日だけこの町で息抜きをしたいと思ったのだが、やはり僕は息抜きってのが出来ないようだ。
デジカメが何故だかARS ELECTRONICAの最終日を待つかのように見事に壊れてしまって、何を撮っても真っ白に飛んでしまうか、あるいは壊れたテレビのように激しく走査線が走った画像しかあらわれない。カメラが壊れたので、まあ休むか、というところなのだけど、幸運にももう1台、手元にカメラがある。こっちは35mmのフィルムカメラ。
あまりにシンプルなつくりなので、相当のことがない限りこちらは壊れない。なので、ウィーンの2日間もただただカメラを持って歩き回ることになるわけだ。(ウェブには載せられないのだけど。)
さて。
僕には、もしもこの町に来ることがあるのなら、いつか必ず行ってみたいと思っていた場所が実は二箇所だけあった。
一箇所は、市庁舎(Rathaus)前にある公園。もう一箇所はシェーンブルン動物園。要するに、ジョン・アーヴィングの小説『熊を放つ』の舞台となった場所だ。主人公のジギーとグラフが出会ったのが市庁舎前公園。そして小説のクライマックス、二人が襲撃する動物園がシェーンブルン動物園なのだ。ウィーンというと他にもきっと有名なものがあるのだろうけれど、僕にはそれくらいしか浮かばない。後は、いつもと同じように、とにかく勘に任せてひたすら歩いて、そして見る、というだけだ。
この『熊を放つ』という作品はこの十数年以上の間、僕にとっては特別な存在であり続けている。僕がバイクに乗りたいと思ったのはこの作品の影響だし、あるいは好みの女の子のタイプもこの小説に影響されたのかもしれない。そして、今でも時々は手にして繰り返し読んでいる。その度に今でも一人でぐっと来たりする。(まあ要するに、僕はとても単純であまり成長しない男なのだ。)
僕は『熊を放つ』を翻訳版で読んでいたのだけど、原作者の才能なのか、あるいは翻訳者の力量なのか、あるいは優れた作家と翻訳者との協働によるものなのか、行ってみて驚いたののは、何故だかどちらも初めて来た感じがさほどしなかったということだ。僕がこの作品を読んだときに勝手に頭の中にイメージしていた風景と殆どそのままだったのだ。シェーンブルン動物園は数年前に大幅な改装が行われたそうで、きっとアーヴィングが見ていた風景とは違うのかもしれないけれど、何故だろうか、とても不思議だった。
ところで、何故動物園を襲撃して熊や他の動物達を開放しようとしたのか。何度も読んでいるくせに、その理由がそこにちゃんと書いてあったのかどうか、実はよく思い出せない。書いてあったような気もするし、あるいは書いてあったとしてもそれは主人公の一人、ジギーのある種出鱈目で無茶苦茶な理屈でしかなかったかもしれない。ともかく、実際にシェーンブルン動物園に行ってみて、何故この動物たちを、しかも熊を開放しなければならなかったのか、なんとなく分かったような気がした。
シェーンブルン動物園はあのハプスブルグ家の離宮・シェーンブルン宮殿の敷地の中にある。シェーンブルン宮殿はもともとは1569年マクシミリアン2世がこの辺りで狩りをするためにつくった館を、その後、ハプスブルグ家の権力を誇示するために、ブルボン家のヴェルサイユ宮殿を勝る規模に拡張させたものらしい。
この宮殿とその敷地はとにかく広い。しかし、動物園はというとそれと対象的でとてもコンパクトなのだ。世界最古の動物園らしいが、動物園として公開されるもっと以前まで遡れば、そもそも狩猟場としてこの土地を手に入れた名残り、つまりそもそも獲物として捉えた動物を入れておく檻として庭園の一角に作られたものなのではないだろうか。何せ広大な敷地があるので、檻が動物園の規模になってしまうわけだ。その意味では、この動物園はそのそも動物たちの生態を観察したり学んだりする場としてつくられた、そもそもパブリックな目的のためにつくられた動物園とは成り立ちが違うといえる。そもそも動物園というものがどのようにして生まれたのかというのことはよく知らないので勝手な憶測でしかないのだが、このシェーンブルン動物園というのは、特に、当時の権力の象徴ということが色濃い反映している存在なのではないかとも思えるのだ。
ジギーとグラフは動物園を襲ったのか。そこには、恐らく動物達が町中を駆け抜ける光景をイメージすると痛快だとか、あるいは単にあまりにも馬鹿げた発想で、それ故に小説のテーマとして魅力的だ、などという理由もきっとあったとは思うが、もしかして、僕が勝手に想像したこんな理由もそこにはいくらかあったのかもしれない。
リンツで見たメディアアートの作品でも、欧州からの出品者の中には、非常に社会的なメッセージが込められた作品が多く見られた。フェスティバルのディレクターであるGerfried Stocker氏にもインタヴューしたときも、彼はそのことが欧州のアーティストのひとつの特徴だということを述べていた。裏返しとして圧倒的に強くのしかかる伝統の強固さというものがそこにはあるのだ、と。
日曜日の朝、リンツの美しい町並を良く見渡せば、石畳の上にあちこちに粉々になって散乱したビール瓶、道沿いの色とりどりの花々の垣根やプランターが荒らされ、花びらが路上に散っている光景を目の当たりにした。
ドナウ川の河畔に集まる若者達の光景は、逆に言えばそこにしか集まる場所がないということでもある。圧倒的に強固な伝統、あるいは権威に対して、如何にして自分の身を置く場所を見つけていくのか、それは最後まで今の日本人には実感できないことなのかもしれない。
 2006.09.04 (Mon) ARS ELECTRONICA
2006.09.04 (Mon) ARS ELECTRONICA
今、オーストリアのリンツという町に来ています。
ARS ELECTRONICAというメディアアート・フェスティバルの取材です。
町の中心地から30分ほど歩いたところのホテルしかとれなくて、毎日てくてくと歩きながら会場に通っています。でも幸いなことに町中に向う途中で市場を発見。毎朝そこでパンやフルーツを買って行き交う人たちを眺めながらベンチに腰掛けて朝食をとるという日課が出来てしまいました。
さてARS ELECTRONICA。様々な作品が出品されていて沢山刺激的な発見があるのですが、個人的には、最終的にシンプルで明快なメッセージが伝わるもの、そしてどこかに社会性という要素があること、そんな作品に惹かれてしまいます。
日本人の作品もとても多いし、きっちりつくってあるのだけど目の前の世界が開けていくダイナミックな感覚というのはあまり感じられませんでした。その意味では器用なんだけど小さくまとまった感じが否めませんでした。でもヨーロッパの人にとってみれば、そういうものがまた面白く見えるんだろうなというのも分かるのだけど。でもこれも国民性というものなんだろうか。
いくつか面白かったものを挙げてみます。
Graffiti Ressearch Labの「High Writer」、「the Drip Sessions」は痛快。そもそもデジタルであるかどうかすら意識させない、もっとフィジカルな部分に訴えかける表現。
Zachary Liebermanの「Drawn」は画像認識のシンプルなプログラミングを用いながら、やはり発想と表現として最終的に見せてくれるかたちがユニークで楽しい。ユーモアのセンスに脱帽でした。
Robotic Chairは、椅子が自らバラバラにぶっ壊れて、バラバラになった部品の状態から再び自ら自動的に組み立て最後は自立するというもの。
今回のARS ELECTRONICAのテーマは「Simplicity」ですが、これはメイン・カンファレンスのオーガナイザーを務めたMITの前田ジョン氏が提唱しているコンセプトであり、当の前田さん本人もビデオインスタレーションで参加していました。今となってはメディアアートの古典的な作品といわれるかもしれないけれど、やはり美しかった。ティルマンズにも通じるものがある気がします。そう思うと、前田作品のような美しさを感じる作品は他にはやはり見当たりませんでした。
じっくり時間をかけてこの数日フェスティバルを見て回っているのですが、やはり集中するためかなかなか疲れます。そんな時は、ドナウ川の河畔の芝生に腰を下ろし、音楽を聞いたり、持ってきた本を読んだりしています。
リンツの町の真ん中にはドナウ川が流れているのですが、これがやはり町の人たちの憩いの場になっていて、夕方近くになると河畔に多くの人が集まって来ます。
面白いのは、高校生くらいの連中も仲間同士つるんで、ビールケースをぶら提げながら集まってくる光景。彼らの写真の撮りながらパンクス風の少年に年齢を尋ねると、なんと13歳。なかなかいいポートレートが撮れた気がします。
さて。明日はウィーンに移動します。
ウィーンといえば、僕の場合は、モーツアルトでも、エゴン・シーレでも、ザッハトルテでもなくて、『Before Sunrise』というイーサン・ホークとジュリー・デュルピーが主演している映画。ただただ偶然に出会った男女二人が町を歩きながら会話しているだけの映画なのですが、何回繰り返してみたことか。エンディングに使われていたダニエル・ジョンストンの楽曲「Living Life」のKathy McCartyによるカバーも好きでした。
僕のiPODにはちょうどEelsがカバーした「Living Life」が入っているので、これを聴きながら移動しようかなと思います。