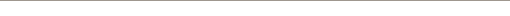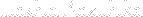沖縄でとんでもないものを観ました。
うるま市勝連町にある与勝中学校、与勝高校生たちが演じる『肝高の阿麻和利』。
これほどまでに眼力(めぢから)がある子供達の表情を、僕は久しく観ていないのではないだろうか。そう思いました。
今、この取材原稿を書いています。原稿は10月中に某誌に掲載されます。
年内中にもまた公演があるようなので、沖縄に行く機会がある方はぜひ体験してみて下さい。
取り急ぎ、沖縄から戻ってきての速報です。

(国立劇場でのリハーサル風景、2005年8月20日)
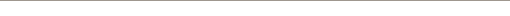 2005.08.20 (Sat) 鳥の眼
2005.08.20 (Sat) 鳥の眼夕方、沖縄に着きました。
明日から、平田大一さんと、沖縄の子供達が演じる「組踊」の取材です。
明日朝一で国立劇場おきなわに行きます。久々にドキドキしています。
羽田空港を離陸した飛行機は東京湾上空を時計周りに旋回し、三浦半島の先端をかすめてゆっくりと高度を上げて飛んでいきます。
三浦半島上空のあたりはまだ高度も低く、城ヶ島も江ノ島も、葉山の御用邸辺りもよく見えます。
そこで、ちょっとだけ遊んでみました。
赤い印は、ほぼ正確にうちの辺りです。
こんな視線で自分が住む場所を見られるというのもなかなか面白いです。

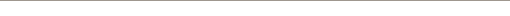 2005.08.18 (Thu) 札幌→旭川→大阪→沖縄
2005.08.18 (Thu) 札幌→旭川→大阪→沖縄取材の仕事が続いています。
僕の場合は、取材といっても、写真撮影だけではなく、取材相手の方にインタヴューし彼らの言葉をまとめることもしています。
写真で撮れるものは写真で、写真には写らないその人の言葉や物語は文字で伝える。
つまりそういうスタンスです。
それは恐らく僕の中では「ストーリー・テリング」ということが一番根っこのテーマとしてあるからだと思います。
先週、札幌のSHIFT、旭山動物園を取材いた後は、
東京・三ノ輪の行燈旅館の撮影。
凄くいいところです。
「旅館というよりも民宿かな」と女将さん。
置かれている調度品も女将さんが長年かけて集められた一品ばかり。
中でも僕には「魯山人の行燈」が堪らなく魅力的でした。
世界中を旅して、一番旅行者にとって居心地のよい空間って何だろう。
女将さんなりの回答が集約されたこの宿に興味がある方はぜひ訪ねてみてください。
今週は今日まで大阪のdigmeoutの谷口さんを取材。
FM802というFMラジオ局の活動ですが、ここのFM局は本当に素晴らしい
姿勢で音楽の魅力を届けてくれるステーションです。
メディアってものが何なのか、FM802、そしてdigmeoutの活動を通じて
改めて考えさせられました。
谷口さんと、大阪・南船場のストリートを散策。
東京より正直パワフルだと感じました。インディペンデントであること、
自分の感覚を頼りに進むことを自然体に行っている人たちに会いました。
中でもイラストレーターでサーファーでもある豊田弘治にもお会いすることが
出来たのはとても嬉しかったです。
それと、今週末からは沖縄に行きます。
平田大一さんという沖縄・小浜島出身の演出家の方を取材してきます。
今、平田さんは沖縄の子供達と一緒に演劇のプロジェクトを手掛けられています。
沖縄は日本の中でも突出して失業率が高く、那覇のような中心地を外れた地方の町に
行けば行くほど、更に失業率は高くなっていきます。
そのことは、大人だけの問題ではなく、子供達にとっても学習意欲の低下を招き、
ひいては地域の活力が萎えていってしまうという状況にも引き起こしていきます。
平田さんは沖縄の伝統的な「組踊(くみおどり)」を平田さんならではの解釈と
アレンジで演出し、沖縄各地の子供達と一緒に舞台公演を展開されています。
ということで、写真展間際というのに、あちこちに出掛けています。
様々な場所で、様々な人たちと出会えることは最高に幸運だと思います。
こうした出会いのひとつひとつを大切にしていきたいと改めて慌しい日々の中で感じました。
彼らから貰ったものは少しずつ書き記して行きたいと思います。
沖縄、いい天気になればいいんだけど。

(Osaka, 2005.08.16.)
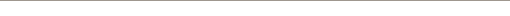 2005.08.16 (Tue) 実りました
2005.08.16 (Tue) 実りました小さな苗から育てていたトマトが、ようやく実をつけました。
すごく嬉しい。

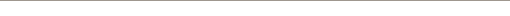 2005.08.12 (Fri) 移りゆく頃
2005.08.12 (Fri) 移りゆく頃今朝、1匹の蝶が、テラスに置いたハーブの鉢の周りを力なく飛んでいるのを見つけた。
(見つけたのは、猫のチロなのだけど。)
暑さのためか寿命のせいか、弱りきったその蝶は殆ど飛ぶことも出来ず、長い舌を出したまま、水を求めて喘いでいた。綿に砂糖水を染み込ませて与えたものの、あまり回復はせず、日中ずっと羽を閉じたままその場に居続けた。
蝉が鳴き出したら、夏本番というよりも、もう夏も終わりなんだな、と思ってしまう。
来週はお盆、よく考えると夏というのは短いのだな。
夕陽を見るためにスクーターに跨ろうとすると、ハンドルに蝉が1匹止まっていた。
そっと掴まえようとすると、その蝉はぽろっと地面にそのままの姿で落ちていった。
スクーターのハンドルに捕まったままの格好でそのまま寿命をまっとうしていたのだ。
翌朝、テラスで蝶の姿は探したが、何処にも見つけられなかった。
夜の間に体力を回復して飛び立ったのだろうか。
それともどこか姿が見られない場所で静かに安らいでいるのだろうか。
心なしか、いつもの刺し込むような夏の陽の光が今日は少し穏やかな気がした。
蝉の鳴き声が昨日より一段と大きく響いている。
少しずつ、でも確かに、季節も、命も、通り過ぎていく。

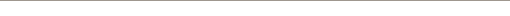 2005.08.10 (Wed) SUMMER BEACH
2005.08.10 (Wed) SUMMER BEACH
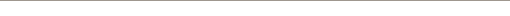 2005.08.06 (Sat) 北海道へ
2005.08.06 (Sat) 北海道へ今週は取材で北海道へ。
水曜日、札幌でShift.orgの大口さんにインタヴュー、その後RocketDesignの菊池君に再会。
ススキノでとても美味しい料理をご馳走になる。
翌日は、早朝7時過ぎのオホーツク1号に乗って旭川へ。
以前から行きたかった旭山動物園を尋ねる。
ひたすらに感動。とにかく良かった。
動物達がこれほど楽しげな表情でいる動物園って初めて観た。
(逆にこれまで見た中で最悪なのは、伊豆高原にある“ねこは博物館”。虐待以外の何者でもない。本当に許すことが出来ない有様。)
旭山動物園は、例えば白い虎のような「客寄せパンダ」など居ないし、決して敷地も広くもないし、アクセスにもとても便利とはいえない。
それでもここは今一番日本で来客数が多い動物園だ。
噂は知っていたが、行ってみてそのことがよく分かった。
「どうやって生き物の自然の姿を伝えていくか。そのために、動物たちが本当にやりたいことは何かを考え、スタッフが知恵を絞ってきた。」という小菅園長の言葉に尽きる。
お金を掛けなくても、大掛かりな仕掛けなどしなくても、
自分達が手にしているものをちゃんと大切に見詰ればいいのだ。
そんな旭山動物園の試みは、僕らの暮らしにも通じるエッセンスがあるような気がする。
ぜひ、お薦めします。

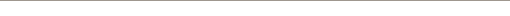 2005.08.03 (Wed) 花火
2005.08.03 (Wed) 花火先週金曜日は逗子海岸の花火大会。
海岸の直ぐ目の前にお住まいのKさん宅から楽しんだ。
K邸の屋根の上に登って、お酒を飲みながら皆で楽しむ花火は本当に最高の時間だった。
それにしても、どうしてこんなにも花火に僕らは熱狂したり、興奮したり、綺麗だなあって思ったりするんだろう。
花火となると大の大人でも胸騒ぎがおさえられなくなって、無邪気な子供のようになってしまう。
僕もその一人だ。
それはきっと眩い閃光として夜空に舞い上がる色とりどりの煌びやかさと同時に、僕らはそこにそれが一瞬でふっと消えてしまう儚さを見るからなんだろう。
それはまるでティーンエージャーが込上げる衝動をその刹那に全てを発散しようとするロックミュージックのようだ。初期衝動が純粋であればあるほど、またそれが刹那的であればあるほど、僕らはそれを美しいと感じるのだ。
写真家のダニー・ライアンに会ったとき、僕は彼から「Bleak Beauty」という言葉を教えてもらった。Bleakとは醜い、惨めな、荒涼としたという意味だ。
「醜と美、一見矛盾しているように思えるけど、そういった相反するものの間にこそ、本当の“美しさ”があるって思うんだ。」 そうダニーは話してくれた。
僕はその言葉がとても好きだ。
Bleak&Beauty、あるいは、Happy & Sad。 あるいは生と死。
花火はまさにそういうものだと思う。
そして、写真も同じだと思う。


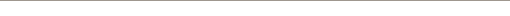 2005.08.01 (Mon) 極東ホテル通信#03
2005.08.01 (Mon) 極東ホテル通信#03ロンドンのカレッジでアートを学んでいるDanと会ったのは金曜日の夜。
僕はその日は仕事が終るのが遅く、ホテルに着いたのは深夜近くだった。
朝早くから出掛ける旅行者達が狭い部屋で薄手の布団に潜り込むのは比較的夜早い時間で、夜中1時過ぎに薄暗い廊下を歩いていたのは僕とDanの2人くらいだった。
唯一まだ消灯されていない洗面所でDanは歯を磨いていた。
僕は彼に話しかけ、ホテルのスタッフのボビーに「静かにね!」と叱られるまで、2人で延々と話し続けた。彼の金色の髪と青い瞳が洗面所の蛍光灯で輝いていた。
僕は彼のポートレートを何枚も撮影した。
「今日街を歩いていたら、ファッション誌のエディターに声を掛けられたんだ。
明日、写真を撮らせて欲しいって。Aって雑誌は知ってる?」
それは良く似た内容で僕には違いがよく分からないけれど、どこかで見覚えのある若者ファッション誌の名前だった。(それがファッション誌なのか、通販カタログ誌なのか正直僕にはよく分からないのだけど。)
「双子の弟はロンドンで時々ファッションモデルをやっている。奴はかなりフェミニンな雰囲気だし。僕も時々声を掛けられるけれど、あまりそういうことには興味はないんだ。連中は僕の写真を撮って稼いでいる。だからちゃんと報酬に僕はお金を貰うようにしている。絵を描くにも、画材やら何やらで、いろいろと掛かるしね。Aのエディターからも、ちゃんと頂くよ。でもKAZはいいよ、アーティスト同士はいつでもどんな時でもフリーなんだ。アーティスト同士はいつもお互いに助け合わなくてはならないんだからね。」
真夜中の洗面所で、ひそひそ声でそんな取り留めもない話を続けたことがお互い妙に可笑しく、まるで修学旅行にでも来ている中学生のようだといって笑っては、またボビーに見つかるんじゃないかと、ハッとして声を潜めあった。そんな風に僕らは長い立ち話を終え、翌朝ロビーで会う約束をしてその夜は隣同士のそれぞれの狭い部屋へと戻った。
翌朝朝早くDanはロビーのインターネットに噛り付いていた。
「今朝、ロンドンの地下鉄で警官がテロの容疑者に発砲したらしいんだ。」
昨夜の冗談交じりに取り留めのない長話をしている時とは、明らかに違う表情の彼が寝起きの僕にそう教えてくれた。(翌週の新聞で、それがとんでもない過ちであったことを僕らは知る。)
僕はその後、睡眠不足と今朝のニュースで青い眼を赤く充血させたDanと、
朝刊を挟んで昨夜とはまた違う話を始めた。昨夜とは違う感触だった。
同じホテルに泊まっているといっても、お互いが挨拶程度しか言葉を交わすことがないというのが殆どの場合だ。例え沢山の言葉を費やして話したからといっても、それで本当のところが見えているのか正直言って僕にはよく分からない。
しかし、そんな僅かな時間の中で、時々お互いの感情が交差したり、相手が放つ感情の閃光のようなものを感じ取る瞬間というのが確かにある。費やした時間や言葉の数ではなく、そんな瞬間を感じ取った時、その相手の存在にそっと触れられたような気がする。
それが確かなものかどうかは分からない。しかしその時、今朝のロンドンのニュースが、僕にとってもごく身近なニュースとして響いてきた、その感覚は確かなものだった。
僕達はまさに蜘蛛の巣のように張り巡らされたネットワークの中に生きている。誰かがそれは神経細胞のようだといった。しかし本当に僕らは遠くで誰かが痛みを感じたら、それを同じように痛みとして感じてられているのだろうか。あるいは誰かが喜びを感じたら、それを自分のことのように喜びを感じてられるというのだろうか。もしそうでないとしたら、それは何を伝えるネットワークなのだろうか。僕達は今、様々な高度に情報化され抽象化する世界の中で、試されているのだと思う。僕達の感性を、相手を想う力を、慈悲や友愛の心を、試されているのだと思う。
他の多くの旅行者達と同様に、僕とDanはその朝のロビー以来、もう暫くは会うことはないだろう。もしかして二度と会わないのかもしれない。
しかし、時々あの朝撮影した写真を僕は見返し、遠くの町に彼が暮らしていることを思い浮べるだろう。まだ見ぬ彼のホームタウンで、彼が暮らしている姿を僕はイメージする。
その度にあの朝のニュースをきっかけに2人で交わした言葉、その感覚が蘇ってくるのだろう。
その時、遠くの国は、もう遠くの国ではないのだ。